2011年01月23日
TPP参加論は「いつか来た道」
TPP推進派の暴走が止まりません。
TPP日米協議 メリット多く参加を急げ
自由貿易圏づくりをめざす環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)をめぐる初の日米事務レベル協議がワシントンで行われた。米国は「従来の自由貿易協定(FTA)を上回る高い目標」を掲げていると説明、日本が交渉に参加する場合は広い分野で自由化を求められる可能性が強まった。
菅直人首相はTPP推進を最重要課題に掲げて第2次改造内閣を発足させたが、米側の要求は予想以上に厳しいとみるべきだ。参加決断を6月に先延ばしせず、早期参加に向けて国内構造改革を果敢に断行してもらいたい。
協議は事実上の日米FTA交渉とも位置付けられた。米側は農業分野を中心に関税の原則撤廃を強調したほか、米国産牛肉輸入制限問題や郵政見直しに伴う外国企業の扱い、自動車の安全技術基準などにも懸念を表明したという。
日本は昨年11月、TPP参加の判断を先送りした上で、「情報収集」目的の事前協議を参加9カ国と行うことにした。今回の協議は豪州などに続いて4カ国目だ。
日米は今後も協議を継続することになったとはいえ、一連の問題にメドをつけなければ日本の交渉参加を拒まれる恐れもある。菅政権は協議結果を真剣に受け止め、農業も含めて「待ったなし」の改革を推進する必要がある。
日米協議が重要なのは、TPPの中身を詰める交渉が米主導でどんどん進められ、11月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)でまとめる強い意向を示しているからだ。米国が日本に示す懸念や注文は、そのままTPP参加へのハードルになる可能性が高い。
日米FTAと同等の意味を持つTPPに参加するメリットは明らかだ。日米の競争力を強化し、長期的な成長を促す基盤を築くだけでなく、世界の通商ルールについて両国のリーダーシップを発揮できる。安全保障面でも日米同盟を補強し、国際ルール無視が目立つ中国を牽制(けんせい)する意味がある。
民主党は日米FTA締結を当初の政権公約に掲げながら、農業団体などの反発で、「締結」を「交渉を促進」に後退させ、TPP参加の決断も先送りした。貿易自由化で影響を受ける農業の保護・強化策は必要だが、こうした腰砕けの姿勢では国民の不信を募らせるだけだ。首相はTPP参加を日本の死活問題と認識し、党内や国民への説得を急ぐべきだ。
(MSN産経ニュースより)
産経には悪いけど、マスゴミ代表として登場していただきました。(念の為申し上げますが、なまくらは産経には「概ね」好意的です。TPPに関しては、マスゴミ全てが賛成派ですが、今回は、単純に他紙のクリック数を稼がせたくなかったので、あえて産経に登場願いました)
この主張のおかしなところは、
・「構造改革」だの「競争力の強化」だの、スローガンばかりで、具体的な根拠やデータが全く示されていない
・「交渉参加を拒まれる」と読者の不安を煽りつつ、メリット・デメリットも吟味せずに「バスに乗り遅れるな」式の主張をしている
・日米安保とTPPを無理やり絡め、まるで「アメリカ様に守ってもらうには、アメリカ様の言うことを問答無用で聞くべきだ」と言わんばかりの主張をしている
こういうやり方、どっかで見覚えがある、と思ったら、戦前の日独伊三国同盟締結時の主張そっくりなんですね。(あるいは「国民が第一」とかスローガンばかりの、どこぞの左翼政党)
こういったスローガン優先の主張に比べ、次に紹介する主張はどうでしょうか?(少々長いです)
「TPPはトロイの木馬」
TPP問題はひとつのテストだと思います。冷戦崩壊から20年が経ち、世界情勢が変わりました。中国・ロシアが台頭し、領土問題などキナ臭くなっています。米国はリーマンショック以降、消費・輸入で世界経済をひっぱることができなくなり、輸出拡大戦略に転じています。世界不況でEUもガタがきていて、どの国も世界の需要をとりにいこうとしています。1929年以降の世界恐慌と同様に危機の時代になるとどの国も利己的になり、とりわけ先進国は世論の支持が必要なので雇用を守るために必死になります。
このような厳しい時代には、日本のような国にもいろいろな仕掛けが講じられるでしょう。その世界の動きの中で日本人が相手の戦略をどう読み、どう動けるかが重要になります。尖閣、北方領土、そしてTPPがきました。このTPP問題をどう議論するか、日本の戦略性が問われていたのですが、ロクに議論もせずあっという間に賛成で大勢が決してしまいました。
─TPPの問題点は
昨年10月1日の総理所信表明演説の前までTPPなんて誰も聞いたことがありませんでした。それにも関わらず政府が11月のAPECの成果にしようと約1ヶ月間の拙速に進めたことは、戦略性の観点だけでなく、民主主義の観点からも異常でした。その異常性にすら気づかず、朝日新聞から産経新聞、右から左まで一色に染まっていたことは非常に危険な状態です。
TPPの議論はメチャクチャです。経団連会長は「TPPに参加しないと世界の孤児になる」と言っていますが、そもそも日本は本当に鎖国しているのでしょうか。
日本はWTO加盟国でAPECもあり、11の国や地域とFTAを結び、平均関税率は米国や欧州、もちろん韓国よりも低い部類に入ります。これでどうして世界の孤児になるのでしょうか。ではTPPに入る気がない韓国は世界の孤児なのでしょうか。
「保護されている」と言われる農産品はというと、農産品の関税率は鹿野道彦農水相の国会答弁によればEUよりも低いと言われています。計算方法は様々なので一概には言えませんが、突出して高いわけではありません。それどころか日本の食糧自給率の低さ、とりわけ穀物自給率がみじめなほど低いのは日本の農業市場がいかに開放されているかを示すものです。何をもって保護と言っているかわかりません。そんなことを言っていると、本当に「世界の孤児」扱いされます。
「TPPに入ってアジアの成長を取り込む」と言いますが、そこにアジアはほとんどありません。環太平洋というのはただの名前に過ぎません。仮に日本をTPP交渉参加国に入れてGDPのシェアを見てみると、米国が7割、日本が2割強、豪州が5%で残りの7カ国が5%です。これは実質、日米の自由貿易協定(FTA)です。
TPPは"徹底的にパッパラパー"の略かと思えるぐらい議論がメチャクチャです。

ニュージーランド、ブルネイ、シンガポール、チリの4加盟国+ベトナム、ペルー、豪州、マレーシア、米国の5参加表明国に日本を加えたGDPグラフ。日本と米国で9割以上を占める。(国連通貨基金(IMF)のHPより作成(2010年10月報告書))
─菅首相は10月当初、TPPをAPECの一つの成果とするべく横浜の地で「開国する」と叫びました
横浜で開国を宣言した菅首相はウィットに富んでいるなと思いました。横浜が幕末に開港したのは日米修好通商条約で、これは治外法権と関税自主権の放棄が記された不平等条約です。その後日本は苦難の道を歩み、日清戦争、日露戦争を戦ってようやく1911年に関税自主権を回復して一流国になりました。中国漁船の船長を解放したのは、日本の法律で外国人を裁けないという治外法権を指します。次にTPPで関税自主権を放棄するつもりであることを各国首脳の前で宣言したのです。
(中略)
─TPPは実質、日米の自由貿易協定(FTA)とおっしゃいましたが、米国への輸出が拡大することは考えられませんか
残念ながら無理です。米国は貿易赤字を減らすことを国家経済目標にしていて、オバマ大統領は5年間で輸出を2倍に増やすと言っています。米国は輸出倍増戦略の一環としてTPPを仕掛けており、輸出をすることはあっても輸入を増やすつもりはありません。これは米国の陰謀でも何でもないのです。
オバマ大統領のいくつかの発言(※1)を紹介します。11月13日の横浜での演説で輸出倍増戦略を進めていることを説明した上で、「...それが今週アジアを訪れた大きな部分だ。この地域で輸出を増やすことに米国は大きな機会を見いだしている」と発言しています。この地域というのはアジアを指しており、TPPのGDPシェアで見れば日本を指しています。そして「国外に10億ドル輸出する度に、国内に5,000人の職が維持される」と、自国(米国)の雇用を守るためにアジア、実質的に日本に輸出するとおっしゃっています。
(中略)
米国の失業率は10%近くあり、オバマ政権はレームタッグ状態です。だからオバマ大統領はどこに行っても米国の選挙民に向けて発言せざるを得ません。
「巨額の貿易黒字がある国は輸出への不健全な異存をやめ、内需拡大策をとるべきだ」とも言っています。巨額の貿易黒字がある国というのは、中国もですけど日本も指しています。そして「いかなる国も米国に輸出さえすれば経済的に繁栄できると考えるべきではない」と続けています。TPPでの日本の輸出先は米国しかなく、米国の輸出先は日本しかない、米国は輸出は増やすけれど輸入はしたくないと言っています。
米国と日本の両国が関税を引き下げたら、自由貿易の結果、日本は米国への輸出を増やせるかもしれないというのは大間違いです。米国の主要品目の関税率はトラックは25%ですが、乗用車は2.5%、ベアリングが9%とトラック以外はそれほど高くありません。日米FTAと言ってもあまり魅力がありません。
─中国と韓国がTPPに参加するという話が一部でありました
中国は米国との間で人民元問題を抱えています。為替操作国として名指しで批判されています。為替を操作するということは貿易自由化以前の話ですから、中国はおそらく入りません。韓国はというと、調整交渉の余地がある二国間の米韓FTAを選択しています。なぜTPPではなくFTAを選んだかというと、TPPの方が過激な自由貿易である上に、加盟国を見ると工業製品輸出国がなく、農業製品をはじめとする一次産品輸出国、低賃金労働輸出国ばかりです。韓国はTPPに参加しても利害関係が一致する国がなく、不利になるから米韓FTAを選んでいるのです
日本は米国とFTAすら結べていないのに、もっとハードルが高く不利な条件でTPPという自由貿易を結ぼうとしています。戦略性の無さが恐ろしいです。
<関税はただのフェイント 世界は通貨戦争>
米国は輸出倍増戦略をするためにドル安を志向しています。世界はグローバル化して企業は立地を自由に選べるので、輸入関税が邪魔であればその国に立地することもできます。現に日本の自動車メーカーは米国での新車販売台数の66%が現地生産で、8割の会社もあります。もはや関税は関係ありません。それに加えて米国は日本の国際競争力を減らしたり、日本企業の米国での現地生産を増やしたりする手段としてドル安を志向します。ドル安をやらないと輸出倍増戦略はできません。
日米間で関税を引き下げた後、ドル安に持って行くことで米国は日本企業にまったく雇用を奪われることがなくなります。他方、ドル安で競争力が増した米国の農産品が日本に襲いかかります。日本の農業は関税が嫌だからといって外国に立地はできず、一網打尽にされるでしょう。グローバルな世界で関税は自国を守る手段ではありません。通貨なんです。
─関税の考え方をかえる必要がありそうです
米国の関税は自国を守るためのディフェンスではなく、日本の農業関税という固いディフェンスを突破するためのフェイントです。彼らはフェイントなどの手段をとれるから日本をTPPに巻き込もうとしているということです。
─農業構造改革を進めれば自由化の影響を乗り越えられるという意見はどう思いますか
みなさんはTPPに入れば製造業は得して農業が損をすると思っているため、農業対策をすればTPPに入れると思うようになります。農業も効率性を上げればTPPに参加しても米国と競争して生き残れる、生き残れないのであれば企業努力が足りない、だから農業構造改革を進めよと言われます。
それは根本的に間違いだと思います。関税が100%撤廃されれば日本の農業は勝てません。関税の下駄がはずれ、米国の大規模生産的農業と戦わざるを得なくなったところでドル安が追い打ちをかけます。さらに米国は不景気でデフレしかかっており、賃金が下がっていて競争力が増しています。関税撤廃、大規模農業の効率性、ドル安、賃金下落という4つの要素を乗り越えられる農業構造改革が思いつく頭脳があるなら、関税があっても韓国に勝てる製造業を考えろと言いたいです。
自由貿易は常に良いものとは限りません。経済が効率化して安い製品が輸入されて消費者が利益を得ることは、全員が認めます。しかし安い製品が入ってきて物価が下がることは、デフレの状況においては不幸なことなのです。デフレというものは経済政策担当者にとって、経済運営上もっともかかってはいけない病だというのが戦後のコンセンサスです。物価が下がって困っている現状で、安い製品が輸入されてくるとデフレが加速します。安い製品が増えて物価が下落して影響を受けるのは農業だけではありません。デフレである日本がデフレによってさらに悪化させられるというのがこのTPP、自由貿易の問題です。
農業構造改革を進めて効率性があがった日には、日本の農家も安い農産物を出荷してしまうことになり、さらにデフレが悪化します。デフレが問題だということを理解していれば、構造改革を進めればいいなんて議論は出てきません。
こういう議論をすると「農業はこのままでいいのか」ということを言い出す人がいます。しかし、デフレの時はデフレの脱却が先なのです。インフレ気味になり、食料の価格が上がるのは嫌なので農業構造改革をするということはアリだと思います。日本は10年以上もデフレです。デフレを脱却することが先に来なければ農業構造改革は手をつけられません。
例えばタクシー業界が競争原理といって規制緩和の構造改革をしました。デフレなのに。その結果、供給過剰でタクシーでは暮らせない人が増えて悲惨なことになりました。今回は同じ事が起ころうとしています。
─TPP参加のメリットを少しだけ...
デメリットは山ほどありますが、メリットはないんです。
米国が輸出を伸ばし日本が輸入を増やして貿易不均衡を直すこと自体は、賛成です。ところが、関税を引き下げて輸入をすると物価が下がるので、日本はデフレが悪化します。経済が縮小するので、結局輸入は増えません。農産品が増えれば米国の農業はハッピーですが、トータルで輸入は増えません。
本当は日本がデフレを脱却して経済を成長させれば、日本の関税は低いんだから輸入が増えるんです。実際に米国はそれをしてほしかったのです。ガイトナー財務長官は昨年6月、日本に内需拡大してくれという書簡を送りました。ところが日本は財政危機が心配だと言って財政出動をしないので、内需拡大をしようとせずに輸出を拡大しようとするので、米国は待ち切れずにTPPに戦略を変えたのでしょう。米国は「とりあえずTPPを進めれば農業は儲かるからいいや」となったのでしょう。
デフレを脱却し、内需を拡大し、経済を成長させれば、関税を引き下げることなく輸入を増やすことができます。環太平洋やアジアの地域は、例えば韓国がGDPの5割以上、中国も3割以上が輸出に頼っており、シンガポールやマレーシアに至ってはGDPよりも輸出が多いです。つまり輸出依存度が高く、その輸出先となっていた米国が輸入したくないと言っているので環太平洋・アジアの国々は困っていることと思います。
今、東アジアが調子が良いのは、資金が流入してバブルになっているからで、本当はヤバイ状況です。環太平洋の国々は経済不況に陥った米国やEUに代わる輸出先を探しています。日本は世界第2位のGDPがあり、GDPにおける輸出の比率は2割以下という内需大国です。その日本が内需を拡大して不況を脱し、名目GDP3%程度の普通の経済成長をしたとすれば、環太平洋の国々は欧米で失った市場の代わりを日本に求めることができるので、本当の環太平洋経済連携ができます。これなら、どの国も不幸になりません。
─あえてTPPを推進する狙いをあげれば、TPP事態は損だとしても今後FTAやEPAなど二国間貿易を進めるきっかけにしたいということなのでしょうか
それも無理筋ですね。自由貿易を進めている国として韓国をあげ、日本はFTAで韓国に遅れをとっているという論調があります。しかしFTAは、一つ一つ戦略的に見ていくべきもので、数で勝ち負けを判断すべきではありません。韓国はGDPの5割以上が輸出で得ており、自由貿易を進めなければ生きていけません。韓国人はやる気があるとか、外を向いているとかいった精神論ではありません。しかし、自由貿易は格差を拡大するものであり、それが進んでしまったのが韓国なのです。
韓国がなぜ競争力があがったかのでしょうか。韓国はこの4年間で円に対するウォンの価値が約半分になっている。韓国の競争力が増したことはウォン安で十分説明できます。日本がTPPで関税を引き下げてもらったとしても、韓国のウォンが10%下がれば同じ事ですし、逆にウォンが上がれば関税があっても十分戦えます。
グローバル化の世界は関税じゃなく通貨だということがここでも言えます。なんで全部農業にツケをまわすんだと言いたいです。とっちにしたって世界不況ですから海外でモノは売れませんよ。失業率が10%の米国で何を売るんですか。
<TPP議論の女性の反応>
─中野さんがおっしゃるような問題点が出されないままに大マスコミが一斉に推進論を展開し、有識者も賛成論がほとんどでした
外国から見ればこんなにカモにしやすい相手はいません。環太平洋パートナーシップ、自由貿易、世界平和など美しいフレーズをつければ日本人はイチコロなんです。
なぜこんなにTPPが盛り上がってしまうのでしょうか。TPPは安全保障のためだという人がいますが、根本的な間違いです。まずTPPは過激な自由貿易協定に過ぎません。軍事協定とは何の関係もありません。
米国はかつての黒船のように武力をちらつかせたり、TPPに入らなければ日米安全保障条約を破棄するなどと言ったりしていません。日米同盟には固有の軍事戦略上の意義があり、経済的な利益のために利用するためのものではありません。さすがに米国でもTPPで農産物の輸出を増やしたいので、その見返りに日本を命をかけて守れと自国の軍隊を説得できませんよ。TPPを蹴ったから日本の領土が危なくなるなんてことはありません。
それにも関わらず日本が勝手にそう思い込んでいるのです。尖閣や北方領土の問題を抱え、軍事力強化は嫌だなと思っているときにTPPが浮かび上がってきて、まさに「溺れる者は藁をもつかむ」ようにTPPにしがみつきました。でもこれにしがみついたって何の関係もないです。もし米国が日米同盟を重視していないのであれば、TPPに入ったって日本を守ってくれません。
その中で無理に理屈をつけようとするから、アジアの成長だの農業構造改革だのと後知恵でくっつけるからきわめて苦しくなるのです。TPP参加論は、単なる強迫観念です。
─推進派が根拠にしているのは経産省が算出したデータです(※2)。どこまで信用できるものなのでしょうか
経産省はTPPに入らなければ10兆円損をするというデータを発表しました。その計算方法は、日本がTPPに入らず、EU、中国とFTAを締結せず、韓国が米国、韓国、EUとFTAを結び発効した場合は10兆円の差が出るというものです。
なぜ中国とEUを入れているのでしょうか。おそらくTPPに加盟しても本当は経済効果がないことがわかったからでしょう。反対派の農水省と賛成派の経産省は数の大きさで争っているので、試算自体に水増しがあります。もっと言えば、なぜTPPとFTAが混ざった試算をするのかが疑問です。日本がTPP で韓国がFTAと試算していることを見れば、韓国がTPPに興味がないことを政府が知っていることがわかります。こんな不自然な試算を見ていると、TPP 参加の理屈をつけるのはさぞかし大変だっただろうなと同情したくなります。
(中略)
─TPPの議論は「思考の停止」が起きているように見えました
議論が複雑でやっかいかもしれませんが、せめてGDP比を見て「TPPは日米貿易に過ぎない」とか、米国が輸出拡大戦略をとろうとして輸入しないようにしているということぐらい知ってもらわないと、戦略を立てようがありません。推進派の人たちが国を開けとか、外を向けとか言っていますが、本当に外を向けば、TPPでは何のメリットもないことがわかるんです。そういう意味では推進派の頭の方が鎖国しています。
この程度の議論は、私みたいな若輩者が言わなくても、偉い先生が言うべきなのに誰も声を上げません、もはや民主主義国家じゃないですよ。
─「反対」はもちろん「わからない」と言いづらい雰囲気がありました
一般の人の方が正常な感覚を持っていたのですが、偉い先生が賛成しているから反対する自信がなかったんだと思います。それこそ下級武士が目を覚ませということで、それにかけるしかない状況です。
(中略)
「明治の開国は関税自主権の回復であり今回はそれを放棄しようとしている」と言うと、多くの女性がまさにその通りと言ってくださいました。女性の方が戦略性というものには敏感なんでしょう。
─日本史を教えている高校教師が「幕末・明治の開国を教えるときは、1911年・小村寿太郎をセットにして教えるほど関税自主権は基本的で大事なこと」と言いました。関税をゼロにするという話に飛びついた政府やマスコミは歴史に何を学んでいるのか疑いたくなります
幕末の開国はペリーが武力で迫ったものですが、今回はそんなことはありません。世界第2位のGDPがあり、何度も言っているようにすでに開国しています。なぜ自爆しようとするのでしょうか。こんな平成の開国の歴史を、僕らの子どもや孫にどうやって教えますか。雰囲気で決めるようなこの時代を、将来、歴史の教科書でどう教えるのですか。
─私は欧米に輸出している液晶モニターメーカーの営業経験がありますが、社員の関税に対するイメージが悪かった思い出があります。EUが関税を引き上げる度に域内の製品価格が上がり売上やマーケットに直結するため非常にセンシティブになります。関税に対するイメージの悪さが、関税撤廃を後押しする雰囲気につながっていることはありませんか
あるかもしれませんね。EUは関税が高いし、戦略的に関税をつかっていますし、そもそもEUはそのための関税同盟です。でも思いだして欲しいのは、 TPPはEUと関係ないんです。日本はEUとFTAを進めたいけどフラれています。それはEUにとって得にならないからです。どの国もひとつひとつ損得を考えて進めているんです。
<迫り来る食糧危機と水不足>
─結局TPPで困る人は?
国民全体です。農業界だけじゃありません。あるいは日本でデフレが進行すれば日本が輸入しなくなり、世界全体も困ります。
心配なのは食料価格の上昇です。世界各国がお金をジャブジャブに供給していて、お金の使い道がないから金や原油の価格が上がっています。食料価格は豪州は洪水と干ばつなどの影響ですでに上昇しており、投機目的でお金が流れてくるとさらに上がることが予想されます。
─TPPの問題は家庭の食卓にも迫ってくるわけですね
1970年代の石油危機がありましたよね。石油の問題はみなさん心配されますが、石油よりも危険なのは食料です。中東の石油は生産量のほとんどを輸出用に回していて、外国に買ってもらわないと経済が成り立たないため、売る側の立場は意外と弱いものです。ところが穀物の場合は、輸出は国内供給のための調整弁でしかなく、不作になれば売らないと言われかねません。
穀物はまず国内を食わせて余剰分を輸出します。当然不作になれば輸出用を減らして国内へまわすものです。もともと農業は天候に左右されるため量と価格が変動しやすく、特に輸出用は調整弁なので変動が大きいのです。変動リスクが大きいから、穀物の国際先物市場が発達したのです。
日本のトウモロコシはほぼ100%米国に依存しているので、僕らは米国の調整弁になっているということです。不作になったら安く売ってもらえなくなります。そのトウモロコシの大生産地である中西部のコーンベルトで起こっていることが、レスター・ブラウンが警告する地下水位の下落です。水不足の問題です。
米国は水不足がわかっているから、ダムのかさ上げ工事を始めています。例えばサンディエゴ市に水を供給するダムは、将来の水不足に備えて市民の1年分の水が追加的に貯められるようになる計画が進められています。米国のフーバーダムひとつで、日本の約2,700のダムの合計貯水量を上回ります。ところが日本は「ダムはムダ」とか言っています。世界が水不足になる中で、日本の水源地はどんどん買われていると聞きます。本当におめでたい国です。
このようにして国は外からでなく内側から滅びるんです。カルタゴを始め、歴史上別に滅びなくてもいいような国がバカをやって滅んでいきました。日本もそういうサイクルに入ったということかもしれませんね。
欧州では「トロイの木馬」の教訓があります。それは「外国からの贈り物には気をつけよう」という言い伝えです。外国から贈り物を受け取るときはまず警戒するものですが、日本はTPPという関税障壁を崩すための「トロイの木馬」を嬉々として受け入れようとしているのです。
<TPP問題の側面にある世代抗争>
こんな状況が広がっている中で、TPP推進派が「日本には戦略が必要だ」と言いながら米国に依存しようとしています。
米国の庇護の下で経済的な豊かさだけを追って、何をしても成功し、ちょっとバカをしても大した損はしなかった世代の人々が90年代以降に企業や政府のトップになり、それ以降日本のGDPが伸びなくなりました。この世代の人たちが「日本の改革のためには外圧が必要だ」「閉塞感を突破するためには刺激が必要だ」という不用意な判断をするので、ものすごい被害を及ぼすことになるのです。
例えば日本は13年連続3万人の自殺者がいます。その前までは、日本は先進国の中でも自殺率が低い国として有名でした。バカなことをすると一気に転げ落ちてしまうんだという真剣さに欠けている人たちが、今の日本を牛耳っているんです。「最近の若者は元気がない」と言う人たちが元気だったのは、彼らが若いころはバブルだったからです。愛読書は「坂の上の雲」と「竜馬が行く」のこの世代は、「開国」と聞くと条件反射的に興奮するようです。
先日朝日新聞社から団塊の世代の方がインタビューに来た時に、彼らの世代の口癖を指摘しました。このままでは日本が危ないという話をすると必ず「そんなことでは日本は壊れない」という口癖です。しかし、日本はもうすでに壊れているんです。政界はもちろん、私も含めた官僚、財界そして知識人は、毎年3 万人の自殺者の霊がとりついていると思うぐらいの責任感をもって、もっと真剣に国の行く末を考えないといけません。
私は1996年に社会人になり、以来、一度も名目GDPの成長を経験していません。私より下の世代はもっとひどい。この世代は「いい加減にしろ」という気持ちになっているのでしょうけど、へたっている上、少子高齢化で上の世代が多すぎて声が出ないんです。でも「最近の若者は元気がない」などと偉そうに言わせてる場合じゃないんです。
今回は地べたを耕している農家、ドブイタ選挙をやっている政治家、女性、この人たちの「危ない!」と思った直感を大切にしなければいけません。全体が賛成派の中で黙っていた人、発言の機会さえ与えられていない人、真剣に生きている人たちに声を上げてもらいたいと思います。(了)
※インタビューの内容は中野氏個人の見解です。
2011年1月14日《THE JOURNAL》編集部取材&撮影
いかがでしょうか?
どちらの主張が、より説得力があったと思いますか?
スローガン「だけ」で議論を挑むマスゴミと、データという「根拠」を持って反論する中野氏。
なまくらは、文句なしに後者ですが。
TPP日米協議 メリット多く参加を急げ
自由貿易圏づくりをめざす環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)をめぐる初の日米事務レベル協議がワシントンで行われた。米国は「従来の自由貿易協定(FTA)を上回る高い目標」を掲げていると説明、日本が交渉に参加する場合は広い分野で自由化を求められる可能性が強まった。
菅直人首相はTPP推進を最重要課題に掲げて第2次改造内閣を発足させたが、米側の要求は予想以上に厳しいとみるべきだ。参加決断を6月に先延ばしせず、早期参加に向けて国内構造改革を果敢に断行してもらいたい。
協議は事実上の日米FTA交渉とも位置付けられた。米側は農業分野を中心に関税の原則撤廃を強調したほか、米国産牛肉輸入制限問題や郵政見直しに伴う外国企業の扱い、自動車の安全技術基準などにも懸念を表明したという。
日本は昨年11月、TPP参加の判断を先送りした上で、「情報収集」目的の事前協議を参加9カ国と行うことにした。今回の協議は豪州などに続いて4カ国目だ。
日米は今後も協議を継続することになったとはいえ、一連の問題にメドをつけなければ日本の交渉参加を拒まれる恐れもある。菅政権は協議結果を真剣に受け止め、農業も含めて「待ったなし」の改革を推進する必要がある。
日米協議が重要なのは、TPPの中身を詰める交渉が米主導でどんどん進められ、11月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)でまとめる強い意向を示しているからだ。米国が日本に示す懸念や注文は、そのままTPP参加へのハードルになる可能性が高い。
日米FTAと同等の意味を持つTPPに参加するメリットは明らかだ。日米の競争力を強化し、長期的な成長を促す基盤を築くだけでなく、世界の通商ルールについて両国のリーダーシップを発揮できる。安全保障面でも日米同盟を補強し、国際ルール無視が目立つ中国を牽制(けんせい)する意味がある。
民主党は日米FTA締結を当初の政権公約に掲げながら、農業団体などの反発で、「締結」を「交渉を促進」に後退させ、TPP参加の決断も先送りした。貿易自由化で影響を受ける農業の保護・強化策は必要だが、こうした腰砕けの姿勢では国民の不信を募らせるだけだ。首相はTPP参加を日本の死活問題と認識し、党内や国民への説得を急ぐべきだ。
(MSN産経ニュースより)
産経には悪いけど、マスゴミ代表として登場していただきました。(念の為申し上げますが、なまくらは産経には「概ね」好意的です。TPPに関しては、マスゴミ全てが賛成派ですが、今回は、単純に他紙のクリック数を稼がせたくなかったので、あえて産経に登場願いました)
この主張のおかしなところは、
・「構造改革」だの「競争力の強化」だの、スローガンばかりで、具体的な根拠やデータが全く示されていない
・「交渉参加を拒まれる」と読者の不安を煽りつつ、メリット・デメリットも吟味せずに「バスに乗り遅れるな」式の主張をしている
・日米安保とTPPを無理やり絡め、まるで「アメリカ様に守ってもらうには、アメリカ様の言うことを問答無用で聞くべきだ」と言わんばかりの主張をしている
こういうやり方、どっかで見覚えがある、と思ったら、戦前の日独伊三国同盟締結時の主張そっくりなんですね。(あるいは「国民が第一」とかスローガンばかりの、どこぞの左翼政党)
こういったスローガン優先の主張に比べ、次に紹介する主張はどうでしょうか?(少々長いです)
「TPPはトロイの木馬」
TPP問題はひとつのテストだと思います。冷戦崩壊から20年が経ち、世界情勢が変わりました。中国・ロシアが台頭し、領土問題などキナ臭くなっています。米国はリーマンショック以降、消費・輸入で世界経済をひっぱることができなくなり、輸出拡大戦略に転じています。世界不況でEUもガタがきていて、どの国も世界の需要をとりにいこうとしています。1929年以降の世界恐慌と同様に危機の時代になるとどの国も利己的になり、とりわけ先進国は世論の支持が必要なので雇用を守るために必死になります。
このような厳しい時代には、日本のような国にもいろいろな仕掛けが講じられるでしょう。その世界の動きの中で日本人が相手の戦略をどう読み、どう動けるかが重要になります。尖閣、北方領土、そしてTPPがきました。このTPP問題をどう議論するか、日本の戦略性が問われていたのですが、ロクに議論もせずあっという間に賛成で大勢が決してしまいました。
─TPPの問題点は
昨年10月1日の総理所信表明演説の前までTPPなんて誰も聞いたことがありませんでした。それにも関わらず政府が11月のAPECの成果にしようと約1ヶ月間の拙速に進めたことは、戦略性の観点だけでなく、民主主義の観点からも異常でした。その異常性にすら気づかず、朝日新聞から産経新聞、右から左まで一色に染まっていたことは非常に危険な状態です。
TPPの議論はメチャクチャです。経団連会長は「TPPに参加しないと世界の孤児になる」と言っていますが、そもそも日本は本当に鎖国しているのでしょうか。
日本はWTO加盟国でAPECもあり、11の国や地域とFTAを結び、平均関税率は米国や欧州、もちろん韓国よりも低い部類に入ります。これでどうして世界の孤児になるのでしょうか。ではTPPに入る気がない韓国は世界の孤児なのでしょうか。
「保護されている」と言われる農産品はというと、農産品の関税率は鹿野道彦農水相の国会答弁によればEUよりも低いと言われています。計算方法は様々なので一概には言えませんが、突出して高いわけではありません。それどころか日本の食糧自給率の低さ、とりわけ穀物自給率がみじめなほど低いのは日本の農業市場がいかに開放されているかを示すものです。何をもって保護と言っているかわかりません。そんなことを言っていると、本当に「世界の孤児」扱いされます。
「TPPに入ってアジアの成長を取り込む」と言いますが、そこにアジアはほとんどありません。環太平洋というのはただの名前に過ぎません。仮に日本をTPP交渉参加国に入れてGDPのシェアを見てみると、米国が7割、日本が2割強、豪州が5%で残りの7カ国が5%です。これは実質、日米の自由貿易協定(FTA)です。
TPPは"徹底的にパッパラパー"の略かと思えるぐらい議論がメチャクチャです。

ニュージーランド、ブルネイ、シンガポール、チリの4加盟国+ベトナム、ペルー、豪州、マレーシア、米国の5参加表明国に日本を加えたGDPグラフ。日本と米国で9割以上を占める。(国連通貨基金(IMF)のHPより作成(2010年10月報告書))
─菅首相は10月当初、TPPをAPECの一つの成果とするべく横浜の地で「開国する」と叫びました
横浜で開国を宣言した菅首相はウィットに富んでいるなと思いました。横浜が幕末に開港したのは日米修好通商条約で、これは治外法権と関税自主権の放棄が記された不平等条約です。その後日本は苦難の道を歩み、日清戦争、日露戦争を戦ってようやく1911年に関税自主権を回復して一流国になりました。中国漁船の船長を解放したのは、日本の法律で外国人を裁けないという治外法権を指します。次にTPPで関税自主権を放棄するつもりであることを各国首脳の前で宣言したのです。
(中略)
─TPPは実質、日米の自由貿易協定(FTA)とおっしゃいましたが、米国への輸出が拡大することは考えられませんか
残念ながら無理です。米国は貿易赤字を減らすことを国家経済目標にしていて、オバマ大統領は5年間で輸出を2倍に増やすと言っています。米国は輸出倍増戦略の一環としてTPPを仕掛けており、輸出をすることはあっても輸入を増やすつもりはありません。これは米国の陰謀でも何でもないのです。
オバマ大統領のいくつかの発言(※1)を紹介します。11月13日の横浜での演説で輸出倍増戦略を進めていることを説明した上で、「...それが今週アジアを訪れた大きな部分だ。この地域で輸出を増やすことに米国は大きな機会を見いだしている」と発言しています。この地域というのはアジアを指しており、TPPのGDPシェアで見れば日本を指しています。そして「国外に10億ドル輸出する度に、国内に5,000人の職が維持される」と、自国(米国)の雇用を守るためにアジア、実質的に日本に輸出するとおっしゃっています。
(中略)
米国の失業率は10%近くあり、オバマ政権はレームタッグ状態です。だからオバマ大統領はどこに行っても米国の選挙民に向けて発言せざるを得ません。
「巨額の貿易黒字がある国は輸出への不健全な異存をやめ、内需拡大策をとるべきだ」とも言っています。巨額の貿易黒字がある国というのは、中国もですけど日本も指しています。そして「いかなる国も米国に輸出さえすれば経済的に繁栄できると考えるべきではない」と続けています。TPPでの日本の輸出先は米国しかなく、米国の輸出先は日本しかない、米国は輸出は増やすけれど輸入はしたくないと言っています。
米国と日本の両国が関税を引き下げたら、自由貿易の結果、日本は米国への輸出を増やせるかもしれないというのは大間違いです。米国の主要品目の関税率はトラックは25%ですが、乗用車は2.5%、ベアリングが9%とトラック以外はそれほど高くありません。日米FTAと言ってもあまり魅力がありません。
─中国と韓国がTPPに参加するという話が一部でありました
中国は米国との間で人民元問題を抱えています。為替操作国として名指しで批判されています。為替を操作するということは貿易自由化以前の話ですから、中国はおそらく入りません。韓国はというと、調整交渉の余地がある二国間の米韓FTAを選択しています。なぜTPPではなくFTAを選んだかというと、TPPの方が過激な自由貿易である上に、加盟国を見ると工業製品輸出国がなく、農業製品をはじめとする一次産品輸出国、低賃金労働輸出国ばかりです。韓国はTPPに参加しても利害関係が一致する国がなく、不利になるから米韓FTAを選んでいるのです
日本は米国とFTAすら結べていないのに、もっとハードルが高く不利な条件でTPPという自由貿易を結ぼうとしています。戦略性の無さが恐ろしいです。
<関税はただのフェイント 世界は通貨戦争>
米国は輸出倍増戦略をするためにドル安を志向しています。世界はグローバル化して企業は立地を自由に選べるので、輸入関税が邪魔であればその国に立地することもできます。現に日本の自動車メーカーは米国での新車販売台数の66%が現地生産で、8割の会社もあります。もはや関税は関係ありません。それに加えて米国は日本の国際競争力を減らしたり、日本企業の米国での現地生産を増やしたりする手段としてドル安を志向します。ドル安をやらないと輸出倍増戦略はできません。
日米間で関税を引き下げた後、ドル安に持って行くことで米国は日本企業にまったく雇用を奪われることがなくなります。他方、ドル安で競争力が増した米国の農産品が日本に襲いかかります。日本の農業は関税が嫌だからといって外国に立地はできず、一網打尽にされるでしょう。グローバルな世界で関税は自国を守る手段ではありません。通貨なんです。
─関税の考え方をかえる必要がありそうです
米国の関税は自国を守るためのディフェンスではなく、日本の農業関税という固いディフェンスを突破するためのフェイントです。彼らはフェイントなどの手段をとれるから日本をTPPに巻き込もうとしているということです。
─農業構造改革を進めれば自由化の影響を乗り越えられるという意見はどう思いますか
みなさんはTPPに入れば製造業は得して農業が損をすると思っているため、農業対策をすればTPPに入れると思うようになります。農業も効率性を上げればTPPに参加しても米国と競争して生き残れる、生き残れないのであれば企業努力が足りない、だから農業構造改革を進めよと言われます。
それは根本的に間違いだと思います。関税が100%撤廃されれば日本の農業は勝てません。関税の下駄がはずれ、米国の大規模生産的農業と戦わざるを得なくなったところでドル安が追い打ちをかけます。さらに米国は不景気でデフレしかかっており、賃金が下がっていて競争力が増しています。関税撤廃、大規模農業の効率性、ドル安、賃金下落という4つの要素を乗り越えられる農業構造改革が思いつく頭脳があるなら、関税があっても韓国に勝てる製造業を考えろと言いたいです。
自由貿易は常に良いものとは限りません。経済が効率化して安い製品が輸入されて消費者が利益を得ることは、全員が認めます。しかし安い製品が入ってきて物価が下がることは、デフレの状況においては不幸なことなのです。デフレというものは経済政策担当者にとって、経済運営上もっともかかってはいけない病だというのが戦後のコンセンサスです。物価が下がって困っている現状で、安い製品が輸入されてくるとデフレが加速します。安い製品が増えて物価が下落して影響を受けるのは農業だけではありません。デフレである日本がデフレによってさらに悪化させられるというのがこのTPP、自由貿易の問題です。
農業構造改革を進めて効率性があがった日には、日本の農家も安い農産物を出荷してしまうことになり、さらにデフレが悪化します。デフレが問題だということを理解していれば、構造改革を進めればいいなんて議論は出てきません。
こういう議論をすると「農業はこのままでいいのか」ということを言い出す人がいます。しかし、デフレの時はデフレの脱却が先なのです。インフレ気味になり、食料の価格が上がるのは嫌なので農業構造改革をするということはアリだと思います。日本は10年以上もデフレです。デフレを脱却することが先に来なければ農業構造改革は手をつけられません。
例えばタクシー業界が競争原理といって規制緩和の構造改革をしました。デフレなのに。その結果、供給過剰でタクシーでは暮らせない人が増えて悲惨なことになりました。今回は同じ事が起ころうとしています。
─TPP参加のメリットを少しだけ...
デメリットは山ほどありますが、メリットはないんです。
米国が輸出を伸ばし日本が輸入を増やして貿易不均衡を直すこと自体は、賛成です。ところが、関税を引き下げて輸入をすると物価が下がるので、日本はデフレが悪化します。経済が縮小するので、結局輸入は増えません。農産品が増えれば米国の農業はハッピーですが、トータルで輸入は増えません。
本当は日本がデフレを脱却して経済を成長させれば、日本の関税は低いんだから輸入が増えるんです。実際に米国はそれをしてほしかったのです。ガイトナー財務長官は昨年6月、日本に内需拡大してくれという書簡を送りました。ところが日本は財政危機が心配だと言って財政出動をしないので、内需拡大をしようとせずに輸出を拡大しようとするので、米国は待ち切れずにTPPに戦略を変えたのでしょう。米国は「とりあえずTPPを進めれば農業は儲かるからいいや」となったのでしょう。
デフレを脱却し、内需を拡大し、経済を成長させれば、関税を引き下げることなく輸入を増やすことができます。環太平洋やアジアの地域は、例えば韓国がGDPの5割以上、中国も3割以上が輸出に頼っており、シンガポールやマレーシアに至ってはGDPよりも輸出が多いです。つまり輸出依存度が高く、その輸出先となっていた米国が輸入したくないと言っているので環太平洋・アジアの国々は困っていることと思います。
今、東アジアが調子が良いのは、資金が流入してバブルになっているからで、本当はヤバイ状況です。環太平洋の国々は経済不況に陥った米国やEUに代わる輸出先を探しています。日本は世界第2位のGDPがあり、GDPにおける輸出の比率は2割以下という内需大国です。その日本が内需を拡大して不況を脱し、名目GDP3%程度の普通の経済成長をしたとすれば、環太平洋の国々は欧米で失った市場の代わりを日本に求めることができるので、本当の環太平洋経済連携ができます。これなら、どの国も不幸になりません。
─あえてTPPを推進する狙いをあげれば、TPP事態は損だとしても今後FTAやEPAなど二国間貿易を進めるきっかけにしたいということなのでしょうか
それも無理筋ですね。自由貿易を進めている国として韓国をあげ、日本はFTAで韓国に遅れをとっているという論調があります。しかしFTAは、一つ一つ戦略的に見ていくべきもので、数で勝ち負けを判断すべきではありません。韓国はGDPの5割以上が輸出で得ており、自由貿易を進めなければ生きていけません。韓国人はやる気があるとか、外を向いているとかいった精神論ではありません。しかし、自由貿易は格差を拡大するものであり、それが進んでしまったのが韓国なのです。
韓国がなぜ競争力があがったかのでしょうか。韓国はこの4年間で円に対するウォンの価値が約半分になっている。韓国の競争力が増したことはウォン安で十分説明できます。日本がTPPで関税を引き下げてもらったとしても、韓国のウォンが10%下がれば同じ事ですし、逆にウォンが上がれば関税があっても十分戦えます。
グローバル化の世界は関税じゃなく通貨だということがここでも言えます。なんで全部農業にツケをまわすんだと言いたいです。とっちにしたって世界不況ですから海外でモノは売れませんよ。失業率が10%の米国で何を売るんですか。
<TPP議論の女性の反応>
─中野さんがおっしゃるような問題点が出されないままに大マスコミが一斉に推進論を展開し、有識者も賛成論がほとんどでした
外国から見ればこんなにカモにしやすい相手はいません。環太平洋パートナーシップ、自由貿易、世界平和など美しいフレーズをつければ日本人はイチコロなんです。
なぜこんなにTPPが盛り上がってしまうのでしょうか。TPPは安全保障のためだという人がいますが、根本的な間違いです。まずTPPは過激な自由貿易協定に過ぎません。軍事協定とは何の関係もありません。
米国はかつての黒船のように武力をちらつかせたり、TPPに入らなければ日米安全保障条約を破棄するなどと言ったりしていません。日米同盟には固有の軍事戦略上の意義があり、経済的な利益のために利用するためのものではありません。さすがに米国でもTPPで農産物の輸出を増やしたいので、その見返りに日本を命をかけて守れと自国の軍隊を説得できませんよ。TPPを蹴ったから日本の領土が危なくなるなんてことはありません。
それにも関わらず日本が勝手にそう思い込んでいるのです。尖閣や北方領土の問題を抱え、軍事力強化は嫌だなと思っているときにTPPが浮かび上がってきて、まさに「溺れる者は藁をもつかむ」ようにTPPにしがみつきました。でもこれにしがみついたって何の関係もないです。もし米国が日米同盟を重視していないのであれば、TPPに入ったって日本を守ってくれません。
その中で無理に理屈をつけようとするから、アジアの成長だの農業構造改革だのと後知恵でくっつけるからきわめて苦しくなるのです。TPP参加論は、単なる強迫観念です。
─推進派が根拠にしているのは経産省が算出したデータです(※2)。どこまで信用できるものなのでしょうか
経産省はTPPに入らなければ10兆円損をするというデータを発表しました。その計算方法は、日本がTPPに入らず、EU、中国とFTAを締結せず、韓国が米国、韓国、EUとFTAを結び発効した場合は10兆円の差が出るというものです。
なぜ中国とEUを入れているのでしょうか。おそらくTPPに加盟しても本当は経済効果がないことがわかったからでしょう。反対派の農水省と賛成派の経産省は数の大きさで争っているので、試算自体に水増しがあります。もっと言えば、なぜTPPとFTAが混ざった試算をするのかが疑問です。日本がTPP で韓国がFTAと試算していることを見れば、韓国がTPPに興味がないことを政府が知っていることがわかります。こんな不自然な試算を見ていると、TPP 参加の理屈をつけるのはさぞかし大変だっただろうなと同情したくなります。
(中略)
─TPPの議論は「思考の停止」が起きているように見えました
議論が複雑でやっかいかもしれませんが、せめてGDP比を見て「TPPは日米貿易に過ぎない」とか、米国が輸出拡大戦略をとろうとして輸入しないようにしているということぐらい知ってもらわないと、戦略を立てようがありません。推進派の人たちが国を開けとか、外を向けとか言っていますが、本当に外を向けば、TPPでは何のメリットもないことがわかるんです。そういう意味では推進派の頭の方が鎖国しています。
この程度の議論は、私みたいな若輩者が言わなくても、偉い先生が言うべきなのに誰も声を上げません、もはや民主主義国家じゃないですよ。
─「反対」はもちろん「わからない」と言いづらい雰囲気がありました
一般の人の方が正常な感覚を持っていたのですが、偉い先生が賛成しているから反対する自信がなかったんだと思います。それこそ下級武士が目を覚ませということで、それにかけるしかない状況です。
(中略)
「明治の開国は関税自主権の回復であり今回はそれを放棄しようとしている」と言うと、多くの女性がまさにその通りと言ってくださいました。女性の方が戦略性というものには敏感なんでしょう。
─日本史を教えている高校教師が「幕末・明治の開国を教えるときは、1911年・小村寿太郎をセットにして教えるほど関税自主権は基本的で大事なこと」と言いました。関税をゼロにするという話に飛びついた政府やマスコミは歴史に何を学んでいるのか疑いたくなります
幕末の開国はペリーが武力で迫ったものですが、今回はそんなことはありません。世界第2位のGDPがあり、何度も言っているようにすでに開国しています。なぜ自爆しようとするのでしょうか。こんな平成の開国の歴史を、僕らの子どもや孫にどうやって教えますか。雰囲気で決めるようなこの時代を、将来、歴史の教科書でどう教えるのですか。
─私は欧米に輸出している液晶モニターメーカーの営業経験がありますが、社員の関税に対するイメージが悪かった思い出があります。EUが関税を引き上げる度に域内の製品価格が上がり売上やマーケットに直結するため非常にセンシティブになります。関税に対するイメージの悪さが、関税撤廃を後押しする雰囲気につながっていることはありませんか
あるかもしれませんね。EUは関税が高いし、戦略的に関税をつかっていますし、そもそもEUはそのための関税同盟です。でも思いだして欲しいのは、 TPPはEUと関係ないんです。日本はEUとFTAを進めたいけどフラれています。それはEUにとって得にならないからです。どの国もひとつひとつ損得を考えて進めているんです。
<迫り来る食糧危機と水不足>
─結局TPPで困る人は?
国民全体です。農業界だけじゃありません。あるいは日本でデフレが進行すれば日本が輸入しなくなり、世界全体も困ります。
心配なのは食料価格の上昇です。世界各国がお金をジャブジャブに供給していて、お金の使い道がないから金や原油の価格が上がっています。食料価格は豪州は洪水と干ばつなどの影響ですでに上昇しており、投機目的でお金が流れてくるとさらに上がることが予想されます。
─TPPの問題は家庭の食卓にも迫ってくるわけですね
1970年代の石油危機がありましたよね。石油の問題はみなさん心配されますが、石油よりも危険なのは食料です。中東の石油は生産量のほとんどを輸出用に回していて、外国に買ってもらわないと経済が成り立たないため、売る側の立場は意外と弱いものです。ところが穀物の場合は、輸出は国内供給のための調整弁でしかなく、不作になれば売らないと言われかねません。
穀物はまず国内を食わせて余剰分を輸出します。当然不作になれば輸出用を減らして国内へまわすものです。もともと農業は天候に左右されるため量と価格が変動しやすく、特に輸出用は調整弁なので変動が大きいのです。変動リスクが大きいから、穀物の国際先物市場が発達したのです。
日本のトウモロコシはほぼ100%米国に依存しているので、僕らは米国の調整弁になっているということです。不作になったら安く売ってもらえなくなります。そのトウモロコシの大生産地である中西部のコーンベルトで起こっていることが、レスター・ブラウンが警告する地下水位の下落です。水不足の問題です。
米国は水不足がわかっているから、ダムのかさ上げ工事を始めています。例えばサンディエゴ市に水を供給するダムは、将来の水不足に備えて市民の1年分の水が追加的に貯められるようになる計画が進められています。米国のフーバーダムひとつで、日本の約2,700のダムの合計貯水量を上回ります。ところが日本は「ダムはムダ」とか言っています。世界が水不足になる中で、日本の水源地はどんどん買われていると聞きます。本当におめでたい国です。
このようにして国は外からでなく内側から滅びるんです。カルタゴを始め、歴史上別に滅びなくてもいいような国がバカをやって滅んでいきました。日本もそういうサイクルに入ったということかもしれませんね。
欧州では「トロイの木馬」の教訓があります。それは「外国からの贈り物には気をつけよう」という言い伝えです。外国から贈り物を受け取るときはまず警戒するものですが、日本はTPPという関税障壁を崩すための「トロイの木馬」を嬉々として受け入れようとしているのです。
<TPP問題の側面にある世代抗争>
こんな状況が広がっている中で、TPP推進派が「日本には戦略が必要だ」と言いながら米国に依存しようとしています。
米国の庇護の下で経済的な豊かさだけを追って、何をしても成功し、ちょっとバカをしても大した損はしなかった世代の人々が90年代以降に企業や政府のトップになり、それ以降日本のGDPが伸びなくなりました。この世代の人たちが「日本の改革のためには外圧が必要だ」「閉塞感を突破するためには刺激が必要だ」という不用意な判断をするので、ものすごい被害を及ぼすことになるのです。
例えば日本は13年連続3万人の自殺者がいます。その前までは、日本は先進国の中でも自殺率が低い国として有名でした。バカなことをすると一気に転げ落ちてしまうんだという真剣さに欠けている人たちが、今の日本を牛耳っているんです。「最近の若者は元気がない」と言う人たちが元気だったのは、彼らが若いころはバブルだったからです。愛読書は「坂の上の雲」と「竜馬が行く」のこの世代は、「開国」と聞くと条件反射的に興奮するようです。
先日朝日新聞社から団塊の世代の方がインタビューに来た時に、彼らの世代の口癖を指摘しました。このままでは日本が危ないという話をすると必ず「そんなことでは日本は壊れない」という口癖です。しかし、日本はもうすでに壊れているんです。政界はもちろん、私も含めた官僚、財界そして知識人は、毎年3 万人の自殺者の霊がとりついていると思うぐらいの責任感をもって、もっと真剣に国の行く末を考えないといけません。
私は1996年に社会人になり、以来、一度も名目GDPの成長を経験していません。私より下の世代はもっとひどい。この世代は「いい加減にしろ」という気持ちになっているのでしょうけど、へたっている上、少子高齢化で上の世代が多すぎて声が出ないんです。でも「最近の若者は元気がない」などと偉そうに言わせてる場合じゃないんです。
今回は地べたを耕している農家、ドブイタ選挙をやっている政治家、女性、この人たちの「危ない!」と思った直感を大切にしなければいけません。全体が賛成派の中で黙っていた人、発言の機会さえ与えられていない人、真剣に生きている人たちに声を上げてもらいたいと思います。(了)
※インタビューの内容は中野氏個人の見解です。
2011年1月14日《THE JOURNAL》編集部取材&撮影
いかがでしょうか?
どちらの主張が、より説得力があったと思いますか?
スローガン「だけ」で議論を挑むマスゴミと、データという「根拠」を持って反論する中野氏。
なまくらは、文句なしに後者ですが。
2011年01月16日
財務省の暴走を止めるのに、小沢派と組めるか?
第2次管改造内閣が発足しました。
この管内閣、保守派ブロガー達が口を極めて非難するのは当然のことですが、面白いことに、ルーピー内閣発足時には民主党マンセーだったブロガーらの一部までもが、この内閣に罵詈雑言を浴びせかけているのです。
彼らもようやく、民主党の危険性に気付き、自分達の主張の稚拙さを反省したのか、と思いきや、どうやらそうではないようです。
彼らが批判するのは、あくまで「管とその内閣」であり、「民主党」ではないのです。
その筆頭とも言える存在が、「植草一秀の『知られざる真実』」。人気ブログランキングで何故かほぼ毎日5位圏内に入っている、「ミラーマン」のブログです。
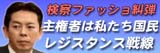
植草は「悪徳ペンタゴン」という造語を用いて「管内閣は政権交代で折角成し遂げた悪徳ペンタゴンの一角「米国」からの独立の流れを逆流させている」と批判、政権を小沢に渡すべきだ」と主張しています。
要は、勝谷と同じ、ただの「小沢シンパ」です。
(因みに「悪徳ペンタゴン」とは、政治屋(政)・特権官僚(官)・大資本(業)・米国(外)・御用メディア(電)を指し、国民を誘導して政権交代を阻止し、既得権益=悪徳権益の甘い蜜を独占しつ続けようと企んでいる悪の軍団のことらしいですww)
さて、この人、「小沢ありき」で、その為のロジックを次から次に編み出していますが、最近の主張は「緊縮財政と消費税を始めとする増税に猛反対!」のようです。
実はこの部分に関して「だけ」は、なまくらも賛同します。
直近の彼の記事を覗いてみましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2011年1月14日 (金)
与謝菅権力亡者内閣は超緊縮大増税突進で自滅へ
1月14日の内閣改造で、菅直人氏は枝野幸男氏を官房長官に、与謝野馨氏を経済財政担当大臣に起用する人事を決定した。驚愕の人事であるが、菅直人内閣の性格が明確に示されたとも言える。
その性格とは、小沢一郎氏に対する執拗な攻撃と、消費税大増税への突進である。
この二つは、いずれも正統性を持たない。
(何故、正統性を持たないか、説明してほしいんですが・・・)
菅直人氏は総選挙後の大連立を視野に入れて本年夏に総選挙に打って出る考えなのだと思われるが、その時点まで菅政権は持たないと思われる。
与謝野馨氏は2009年8月の総選挙で小選挙区候補として落選した。その後、自民党枠の比例復活で辛うじて復活当選を得た人物である。出自に照らし、自民党議員であり、国民主権の原理に照らし、自民党に投票した主権者に対して責任を負う立場にある。
その人物が、政党を渡り歩き、ポストを求めてさまよう姿は「老害」以外の何者でもない。
(確かに、その通りです。比例復活した議員が1度ならず2度までも所属政党を裏切ることは、選挙制度上、問題あると思います。)
予算委員会質疑では、鳩山由紀夫前首相に対して「平成の脱税王」と罵っていたが、与謝野氏自身が多額の迂回献金を受け取ったり、職務権限との抵触が疑われる企業から献金を受け取ったことが明らかにされるなど、限りなく真っ黒に近い人物でもある。
国会質疑では鳩山邦夫議員から聞いた話だと、架空の話をねつ造して質問したこともある、人間としても信用できない代表的人物である。
ただ、権力とポストに対する妄執だけはすさまじいようだ。この点で菅直人氏と瓜二つである。
(ちょっwwおまっww汚沢に関しては散々「検察の横暴」だの「陰謀」だの唱えているくせに、汚沢以外は「疑惑をかけられた時点でアウト」ですかwwしかも、「権力とポストに対する妄執だけはすさまじい」って、汚沢に向けて言ってるのかと思ったよww)
菅直人氏はすでに魂を米国に売り渡しているから、中味はほとんどすっから菅である。
残っているのは、
①権力とポストへの妄執
②小沢氏に対する敵意
③消費税大増税への突撃精神
だけであると思われる。
菅直人氏が与謝野氏を経済財政担当相に起用したのは、消費税大増税をつなぎに大連立を模索するためである。
(「大連立の為のつなぎ」という読みは、確かに「あり」かもです)
しかし、この基本方針は2009年8月の総選挙における民主党マニフェストそのものの全面否定である。
三つの重大な問題がある。
第一は、2011年度予算が史上空前のデフレ予算であり、追加デフレ策を打たなくても日本経済は2011年に確実に悪化することが確実であることだ。
(「追加デフレ策を打っても」の間違いでしょうか?確かに、公共事業などの従来型の景気対策項目は減らされています)
マーケットエコノミストは財政計数の読み方を知らないらしい。2011年度予算が超デフレ予算であることを指摘する声がない。つまり、市場はまだこの重大事実を織り込んでいない。
(確かに、内国債がデフォルトする、などと真顔で言うメディア露出エコノミスト(S坊やI崎など)達に踊らされるマスコミは、デフレの恐怖をきちんと国民に伝えようとしていません)
『金利・為替・株価特報』2011年1月14日号に詳述するが、必ず、強烈なインパクトが表面化することになるだろう。
このなかで、消費税大増税を決めれば、何が起こるのかは自明だ。経済が呼吸停止の状態に陥るのは必定である。
(同意。橋本政権が行った消費税増税時の二の舞になるのは火を見るより明らかです)
第二は、消費税増税の前提条件がまったく満たされていないことだ。2009年8月の総選挙で鳩山前首相は、増税検討の前に政府支出の無駄排除をやり抜くことを主権者に約束した。この公約はまだ生きている。菅直人氏の方針はこの公約の全面破棄である。
事業仕分けは政府支出が無駄の塊であることを示しただけで、肝心な無駄の排除はまったく進んでいない。
(ハア?「10兆円は無駄がある筈だ」とか総選挙前に豪語していたくせに、蓋を開けてみれば小鳩政権はたった3兆円(しかも、やっとかっとひねり出して)しか「無駄」を見つけられなかったじゃないか。確かに、ほとんどが貯金に回って、一向に消費支出拡大(=景気回復)に貢献しない「子ども手当」が無駄の塊であることだけは示せたよなw「消費税増税の前提条件が満たされていない」というのは同意だが、なまくらの考える「前提条件」とは、「日本経済のインフレステージへの移行」です)
第三は、政府支出の無駄を排除しないのに消費税増税に進むことについて、すでに主権者が明確にNOの意思を表明していることだ。
2010年7月参院選で、主権者国民は菅直人氏の消費税増税公約にNOを突き付けた。菅直人氏は、この段階で辞任しなければならなかったが、ウソを塗り固めて総理の座にしがみついている。
(消費税が原因で大敗したと言うなら、同じく消費増税を掲げた自民党の議席が増えた理由をきちんと整理してください)
与謝野氏はミスター老害と呼ぶべき存在だ。2008年のリーマンショックを「蚊に刺された程度」と診断し、政策対応が後手に回ったことが日本経済崩壊加速の主因になった。
不況が深刻だと分かると、今度は無駄遣いてんこ盛りの14兆円補正予算を編成して、日本財政を破壊した。
財政を破壊しておいて、今度は大増税に突き進む。放火犯が放火したあとで、はしご付き消防車が必要だと騒いでいるのに等しい。経済政策運営音痴なのだ。
憲法もあり、国民主権を定めてもいるのに、主権者国民の意思を無視した政治の暴走を、もうこれ以上許すわけにはいかない。
与謝菅権力亡者内閣は本年なかばまでに自損事故で消滅することになるだろう。大事なことは、そのあとに、確実に主権者国民政権を再樹立することだ。主権者国民勢力の結集が急務である。
(なまくらも、管内閣は早ければ統一地方選前後に総辞職するだろう、と思っていますが、少なくともあなたの言う「主権者国民政権」が汚沢政権でないことだけは確実です)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上見てきたように、植草を初め、小沢シンパブロガーの多くは「緊縮財政反対派」です。(それもそのはず、小沢シンパブロガー=植草シンパブロガーですから)
はっきり言って財政問題以外では、なまくらと真逆の主張をしているわけですが、こと経済財政問題に関しては奇妙に一致するのです。
なまくらは過去の記事でも書いてきた通り、財務省主導の「財政再建政策」はデフレ下では完全に間違いであると思っているわけです。
今日も書店で「日本は3年後に破綻する!」なんて書いている本を目にしましたが、国際政治的には兎も角、財政的に破綻(要はデフォルトやハイパーインフレ)することなど、まずあり得ません。(そして、3年後に破綻しなくても、破綻論者達は誰も責任をとりません)
何せ、「内国債の増大でデフォルトすることはない」と、当の財務省が海外の格付け機関に意見を述べているのですから!(そして、国内向けには延々と「国債がデフォルトする」と嘘をつき続けています)
そして、今は財政再建の為の緊縮予算と増税なんて、するべきではなく、むしろ積極財政を進めることが必要だ、と思っているわけです。
デフレという「死に至る病」を克服する為には、子ども手当や農家の戸別補償など、いわゆる民主党のばら撒き政策ですら、やらないよりはマシ、だと思います。
(もっとも、もっと有効な使い道があるから反対しますが)
しかし、こういった積極財政を唱える声は、財務省とその記者クラブを構成するマスゴミによって、「抵抗勢力」と貶められているのです。
要は、ことデフレ問題に関しては、敵の本丸は財務省なのです。そして、この問題について、なまくらと共通認識を持っているのが、植草を初めとする小沢派なのです。
彼らの場合、「官僚=悪」であり、その総本山が財務省である、と看做して、そこに至るロジックに財政問題を位置付けている点がなまくらと視点が少し違うのですが、今は財務省主導の「財政再建政策」が間違いである、と考えている点は同じなのです。
要は、「強い日本経済の復活」を考えている部分は、保守派も小沢派も同じなんですね。
だったら小沢派と組めるか、と言うと、なかなか難しいんですね。
最大の障碍は、小沢派が 中共に対する警戒心が決定的に薄い ということです。
これはもう、致命傷ですね。あの尖閣沖衝突事件や去年の2回にわたる北チョンの挑発行動すら、彼らにかかれば「ユダヤ金融とその手先アメリカによる陰謀」なのですから、あいた口がふさがりません。
陰謀論を唱えるなら、もうちょっと根拠を示してほしいものですが、そんなもの、彼らの脳内にしかないのだから、他者への説得力ゼロです。
財務省主導の「財政破綻世論」を覆すには、彼らの協力も欲しいところですが、さて・・・
この管内閣、保守派ブロガー達が口を極めて非難するのは当然のことですが、面白いことに、ルーピー内閣発足時には民主党マンセーだったブロガーらの一部までもが、この内閣に罵詈雑言を浴びせかけているのです。
彼らもようやく、民主党の危険性に気付き、自分達の主張の稚拙さを反省したのか、と思いきや、どうやらそうではないようです。
彼らが批判するのは、あくまで「管とその内閣」であり、「民主党」ではないのです。
その筆頭とも言える存在が、「植草一秀の『知られざる真実』」。人気ブログランキングで何故かほぼ毎日5位圏内に入っている、「ミラーマン」のブログです。
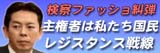
植草は「悪徳ペンタゴン」という造語を用いて「管内閣は政権交代で折角成し遂げた悪徳ペンタゴンの一角「米国」からの独立の流れを逆流させている」と批判、政権を小沢に渡すべきだ」と主張しています。
要は、勝谷と同じ、ただの「小沢シンパ」です。
(因みに「悪徳ペンタゴン」とは、政治屋(政)・特権官僚(官)・大資本(業)・米国(外)・御用メディア(電)を指し、国民を誘導して政権交代を阻止し、既得権益=悪徳権益の甘い蜜を独占しつ続けようと企んでいる悪の軍団のことらしいですww)
さて、この人、「小沢ありき」で、その為のロジックを次から次に編み出していますが、最近の主張は「緊縮財政と消費税を始めとする増税に猛反対!」のようです。
実はこの部分に関して「だけ」は、なまくらも賛同します。
直近の彼の記事を覗いてみましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2011年1月14日 (金)
与謝菅権力亡者内閣は超緊縮大増税突進で自滅へ
1月14日の内閣改造で、菅直人氏は枝野幸男氏を官房長官に、与謝野馨氏を経済財政担当大臣に起用する人事を決定した。驚愕の人事であるが、菅直人内閣の性格が明確に示されたとも言える。
その性格とは、小沢一郎氏に対する執拗な攻撃と、消費税大増税への突進である。
この二つは、いずれも正統性を持たない。
(何故、正統性を持たないか、説明してほしいんですが・・・)
菅直人氏は総選挙後の大連立を視野に入れて本年夏に総選挙に打って出る考えなのだと思われるが、その時点まで菅政権は持たないと思われる。
与謝野馨氏は2009年8月の総選挙で小選挙区候補として落選した。その後、自民党枠の比例復活で辛うじて復活当選を得た人物である。出自に照らし、自民党議員であり、国民主権の原理に照らし、自民党に投票した主権者に対して責任を負う立場にある。
その人物が、政党を渡り歩き、ポストを求めてさまよう姿は「老害」以外の何者でもない。
(確かに、その通りです。比例復活した議員が1度ならず2度までも所属政党を裏切ることは、選挙制度上、問題あると思います。)
予算委員会質疑では、鳩山由紀夫前首相に対して「平成の脱税王」と罵っていたが、与謝野氏自身が多額の迂回献金を受け取ったり、職務権限との抵触が疑われる企業から献金を受け取ったことが明らかにされるなど、限りなく真っ黒に近い人物でもある。
国会質疑では鳩山邦夫議員から聞いた話だと、架空の話をねつ造して質問したこともある、人間としても信用できない代表的人物である。
ただ、権力とポストに対する妄執だけはすさまじいようだ。この点で菅直人氏と瓜二つである。
(ちょっwwおまっww汚沢に関しては散々「検察の横暴」だの「陰謀」だの唱えているくせに、汚沢以外は「疑惑をかけられた時点でアウト」ですかwwしかも、「権力とポストに対する妄執だけはすさまじい」って、汚沢に向けて言ってるのかと思ったよww)
菅直人氏はすでに魂を米国に売り渡しているから、中味はほとんどすっから菅である。
残っているのは、
①権力とポストへの妄執
②小沢氏に対する敵意
③消費税大増税への突撃精神
だけであると思われる。
菅直人氏が与謝野氏を経済財政担当相に起用したのは、消費税大増税をつなぎに大連立を模索するためである。
(「大連立の為のつなぎ」という読みは、確かに「あり」かもです)
しかし、この基本方針は2009年8月の総選挙における民主党マニフェストそのものの全面否定である。
三つの重大な問題がある。
第一は、2011年度予算が史上空前のデフレ予算であり、追加デフレ策を打たなくても日本経済は2011年に確実に悪化することが確実であることだ。
(「追加デフレ策を打っても」の間違いでしょうか?確かに、公共事業などの従来型の景気対策項目は減らされています)
マーケットエコノミストは財政計数の読み方を知らないらしい。2011年度予算が超デフレ予算であることを指摘する声がない。つまり、市場はまだこの重大事実を織り込んでいない。
(確かに、内国債がデフォルトする、などと真顔で言うメディア露出エコノミスト(S坊やI崎など)達に踊らされるマスコミは、デフレの恐怖をきちんと国民に伝えようとしていません)
『金利・為替・株価特報』2011年1月14日号に詳述するが、必ず、強烈なインパクトが表面化することになるだろう。
このなかで、消費税大増税を決めれば、何が起こるのかは自明だ。経済が呼吸停止の状態に陥るのは必定である。
(同意。橋本政権が行った消費税増税時の二の舞になるのは火を見るより明らかです)
第二は、消費税増税の前提条件がまったく満たされていないことだ。2009年8月の総選挙で鳩山前首相は、増税検討の前に政府支出の無駄排除をやり抜くことを主権者に約束した。この公約はまだ生きている。菅直人氏の方針はこの公約の全面破棄である。
事業仕分けは政府支出が無駄の塊であることを示しただけで、肝心な無駄の排除はまったく進んでいない。
(ハア?「10兆円は無駄がある筈だ」とか総選挙前に豪語していたくせに、蓋を開けてみれば小鳩政権はたった3兆円(しかも、やっとかっとひねり出して)しか「無駄」を見つけられなかったじゃないか。確かに、ほとんどが貯金に回って、一向に消費支出拡大(=景気回復)に貢献しない「子ども手当」が無駄の塊であることだけは示せたよなw「消費税増税の前提条件が満たされていない」というのは同意だが、なまくらの考える「前提条件」とは、「日本経済のインフレステージへの移行」です)
第三は、政府支出の無駄を排除しないのに消費税増税に進むことについて、すでに主権者が明確にNOの意思を表明していることだ。
2010年7月参院選で、主権者国民は菅直人氏の消費税増税公約にNOを突き付けた。菅直人氏は、この段階で辞任しなければならなかったが、ウソを塗り固めて総理の座にしがみついている。
(消費税が原因で大敗したと言うなら、同じく消費増税を掲げた自民党の議席が増えた理由をきちんと整理してください)
与謝野氏はミスター老害と呼ぶべき存在だ。2008年のリーマンショックを「蚊に刺された程度」と診断し、政策対応が後手に回ったことが日本経済崩壊加速の主因になった。
不況が深刻だと分かると、今度は無駄遣いてんこ盛りの14兆円補正予算を編成して、日本財政を破壊した。
財政を破壊しておいて、今度は大増税に突き進む。放火犯が放火したあとで、はしご付き消防車が必要だと騒いでいるのに等しい。経済政策運営音痴なのだ。
憲法もあり、国民主権を定めてもいるのに、主権者国民の意思を無視した政治の暴走を、もうこれ以上許すわけにはいかない。
与謝菅権力亡者内閣は本年なかばまでに自損事故で消滅することになるだろう。大事なことは、そのあとに、確実に主権者国民政権を再樹立することだ。主権者国民勢力の結集が急務である。
(なまくらも、管内閣は早ければ統一地方選前後に総辞職するだろう、と思っていますが、少なくともあなたの言う「主権者国民政権」が汚沢政権でないことだけは確実です)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上見てきたように、植草を初め、小沢シンパブロガーの多くは「緊縮財政反対派」です。(それもそのはず、小沢シンパブロガー=植草シンパブロガーですから)
はっきり言って財政問題以外では、なまくらと真逆の主張をしているわけですが、こと経済財政問題に関しては奇妙に一致するのです。
なまくらは過去の記事でも書いてきた通り、財務省主導の「財政再建政策」はデフレ下では完全に間違いであると思っているわけです。
今日も書店で「日本は3年後に破綻する!」なんて書いている本を目にしましたが、国際政治的には兎も角、財政的に破綻(要はデフォルトやハイパーインフレ)することなど、まずあり得ません。(そして、3年後に破綻しなくても、破綻論者達は誰も責任をとりません)
何せ、「内国債の増大でデフォルトすることはない」と、当の財務省が海外の格付け機関に意見を述べているのですから!(そして、国内向けには延々と「国債がデフォルトする」と嘘をつき続けています)
そして、今は財政再建の為の緊縮予算と増税なんて、するべきではなく、むしろ積極財政を進めることが必要だ、と思っているわけです。
デフレという「死に至る病」を克服する為には、子ども手当や農家の戸別補償など、いわゆる民主党のばら撒き政策ですら、やらないよりはマシ、だと思います。
(もっとも、もっと有効な使い道があるから反対しますが)
しかし、こういった積極財政を唱える声は、財務省とその記者クラブを構成するマスゴミによって、「抵抗勢力」と貶められているのです。
要は、ことデフレ問題に関しては、敵の本丸は財務省なのです。そして、この問題について、なまくらと共通認識を持っているのが、植草を初めとする小沢派なのです。
彼らの場合、「官僚=悪」であり、その総本山が財務省である、と看做して、そこに至るロジックに財政問題を位置付けている点がなまくらと視点が少し違うのですが、今は財務省主導の「財政再建政策」が間違いである、と考えている点は同じなのです。
要は、「強い日本経済の復活」を考えている部分は、保守派も小沢派も同じなんですね。
だったら小沢派と組めるか、と言うと、なかなか難しいんですね。
最大の障碍は、小沢派が 中共に対する警戒心が決定的に薄い ということです。
これはもう、致命傷ですね。あの尖閣沖衝突事件や去年の2回にわたる北チョンの挑発行動すら、彼らにかかれば「ユダヤ金融とその手先アメリカによる陰謀」なのですから、あいた口がふさがりません。
陰謀論を唱えるなら、もうちょっと根拠を示してほしいものですが、そんなもの、彼らの脳内にしかないのだから、他者への説得力ゼロです。
財務省主導の「財政破綻世論」を覆すには、彼らの協力も欲しいところですが、さて・・・
2009年12月09日
民主憎けりゃ財政出動まで憎し?
産経新聞は、ゴミ溜めのような新聞業界にあって、最もまともな新聞だと思います。
立ち位置としては「やや保守寄りの中立」であり、ナベツネ支配の読売新聞よりもはるかに好感が持てます。
ただし、なまくらが「おや?」と思うスタンスも幾つかあります。
一つは「親米」を追求し過ぎて自主独立の気概を失くしている事、もう一つは「小泉構造改革マンセー」な点です。
何でもかんでも「自己責任」論を展開し、「小さな政府」、「規制緩和」、「官から民へ」という米共和党的発想を紙面にぶちまける姿は、「親米紙ここにあり」と言っているようで、正直辟易する事もあります。
先日も、このような連載記事を臆面もなく掲載していました。
【デフレの恐怖】(下)日本経済は「低体温症」 頼みは構造改革と成長戦略
(前略)
■続く物価下落
「日本経済が陥っている状況は、まさに低体温症だ」と話すのは、日本総合研究所の湯元健治理事だ。
経済で体温と形容される物価は、このところ下落を続けている。9月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比2・3%の下落で、7カ月連続の前年割れだ。
「先進国では2~3%成長するのが平熱だが、日本はせいぜい1~2%で、悪ければマイナスになる。現状では恒常的な物価下落の状況にあるうえ、慢性的な低成長と税収の縮小に見舞われている。いずれも低体温症によるものだ」(湯元氏)
政策を実行するための資金を確保しようとしても税収が不足している。それをカバーするために国債を増発すれば、償還負担が重くなる。その結果、低成長に至る。デフレという名の低体温症はこの悪循環を慢性化させる。

10月30日に日本銀行が公表した「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」も、日本の潜在成長率を「0%台半ば」とした。景気後退でモノが売れず、企業の設備投資が伸び悩んだためで、4月時点の「1%前後」から下方修正した。
■脱出策は市場拡大
脱出策はあるのか。
湯元氏は「先行きの成長を期待させる政策があれば脱出可能だ」と話す。そのひとつが、小泉内閣で着手した「官から民へ」「中央から地方へ」「貯蓄から投資へ」など構造改革の徹底だ。「国のムダを省き効率的にすることから展望が開ける」と指摘する。
また国内の市場縮小の底流にある人口減少に対応するため、「外国人労働者の導入も本気で検討する必要がある」という。
関西大大学院会計研究科の宮本勝浩教授も市場拡大策を練るべきだと話す。「民主党政権が掲げる富の再配分は重要だが、成長産業を後押しする規制緩和を集中的に進めるなど、経済の成長戦略がなければ低体温症から抜け出すのは難しい。金融政策も重要だ」と指摘する。
大手メーカー幹部は「多くの輸出企業は円高リスクに対応するため体質強化を続けてきた。日本政府が慢性的なデフレへの対策を怠れば、企業は海外に出ていくしかない」と話す。そのうえで、こう言い切った。
「政策はいろいろと検討の余地があるだろう。しかしもっとも大事なのは、低体温症から抜け出す、という固い意志だ」
(MSN産経ニュースより転載)
日本経済が低体温症に陥っているという状況認識は、まあ良いとして、
>国債を増発すれば、償還負担が重くなる。その結果、低成長に至る。
という論理展開は、はっきり言って滅茶苦茶です。
そもそも、償還負担云々と書いている時点で、国の債務と個人や私企業の債務の区別が全くついていません。
三橋貴明氏や廣宮孝信氏の書籍・ブログをほんの少しでも読んだ事がある人なら、もうお分かりのように、現在の日本国国債は100%円建てであり、外貨建てではありません。そのメリットは、何と言っても延々と繰り延べ(ロールオーバー)出来る点にあります。
つまり、償還負担が重くなる事など、経済成長する限り、これっぽっちも起こらないのです。
さらに、国債増発(財政出動)→償還負担が重くなる→低成長という流れは、全くもってワケワカメです。普通なら、国債増発(財政出動)→GDPが持ち直す→経済成長となるのではないでしょうか?
それなのに、景気対策で財政出動しておきながら、どうして低成長(≒不景気)となるのか、論理が飛躍しすぎていて、付いていけません。
思うに、この行燈記事を書いた記者は、
民主党政権は嫌だ!→鳩山内閣がする事なす事全て批判してやれ→「平成22年度当初予算95兆円」は格好の標的→「民主党政権で財政破綻」キャンペーン
という思考回路となっているのではないでしょうか?
こんな脳内フィルターをかけて記事を書くなら、「自民党政権で財政破綻」キャンペーンの朝日新聞と何ら変わりがありません。
そして、挙句の果てに、
「デフレスパイラルから抜け出すために、”官から民へ””中央から地方へ””貯蓄から投資へ”など構造改革を徹底しろ!」
とホザきます。
なまくらは、この竹中式思考回路に茫然自失してしまったので、反論は三橋さんにしていただくことにします。↓
「主問題経済下(三橋注:通常経済下)においては、リカードの比較優位説が作動し、貿易が正当化され、グローバリゼーションが正しい政策になります。このときは、グローバリゼーションにより全てのプレーヤーが豊かになります。
一方、双対問題経済下(三橋注:恐慌経済下)においては、リカードの比較優位説は作動せず、貿易は正当化されず、鎖国が正しい政策になります。このときグローバリゼーションを行えば、すべてのプレーヤーが貧しくなります。(経済学はなぜ間違えるのか P146)」
(中略)
「いや。このまま自由貿易を続け、グローバリゼーションを推し進めれば、あなた方の問題はきっと解決します」
などと言えるはずがありません。自由貿易を続けても、中国などからどんどん安い製品が入ってくるだけで、国内の雇用環境は確実に悪化します。
もちろん、アメリカ政府は財政出動を行い、国内の景気の下支えをしようとするでしょう。しかし、政府が「国民のお金(あえて血税とは書きませんが)」を使い、国内に需要を作り出したとして、自由貿易を続けると、折角苦労して創出した需要を海外諸国に奪われる(輸入増、という形で)結果になってしまうのです。輸入とは、その国のGDPの「控除項目」です。輸入が一方的に増えれば、GDPがその分だけ減少し、国内の需要が奪われてしまいます。
はい。重要な部分なので、しつこく書きます。
「輸入とは、自国の需要を他国に奪われることです。そして輸出とは、他国の需要を奪い取る行為なのです」
(中略)
アメリカの場合は(日本もですが)、ここに「グローバル化されてしまった金融」という問題が加わります。すなわち、上記の読売の記事に登場した人々を助けようと、政府が国内にお金を大量に供給しても、それが金融のグローバルプレーヤー(要はウォール街)により、海外投資に持ち出されてしまうという問題です。
(中略)
グローバル化の進展は、通常経済のフェーズでは有利に働きますが、恐慌経済下では国内の雇用や需要が奪われ、不利に働きます。実践主義の戦略家ぞろいのアメリカが、この事実に気がついていないはずがありません(と言うか、政府首脳部が気がつかずとも、議員は気がつきます)。そろそろ表立って「保護主義」の議論が始まるのではないかなあ、と、予感がしています。
(新世紀のビッグブラザーへBlog「グローバリズムの罠 その1 その2」より一部転載)
構造改革路線が目指す先にはクローバリズムがあるので、産経への批判は上記ブログで既に行われている事がお分かりいただけたでしょうか?
その前にも、
今年、様々な新聞関係者とお会いしましたが、誰もが口をそろえたように、
「産経新聞は名前に『経済』が入っているが、おそらく最も経済について無知な新聞社だ」
と言うのも無理もありません。(但し、面白いことに、皆必ず「田村秀男さんは除くが・・・」と付け加えるのです)
とありましたが、思わず「確かに」と頷いてしまいました。
産経新聞よ、折角、外交・安全保障面で素晴らしい記事を書くのだから、そっちに注力して、経済・財政問題は担当をリストラして田村秀男さん一人に任せてしまいなさい。
そうした方が、きっと早く業績回復できますから。
立ち位置としては「やや保守寄りの中立」であり、ナベツネ支配の読売新聞よりもはるかに好感が持てます。
ただし、なまくらが「おや?」と思うスタンスも幾つかあります。
一つは「親米」を追求し過ぎて自主独立の気概を失くしている事、もう一つは「小泉構造改革マンセー」な点です。
何でもかんでも「自己責任」論を展開し、「小さな政府」、「規制緩和」、「官から民へ」という米共和党的発想を紙面にぶちまける姿は、「親米紙ここにあり」と言っているようで、正直辟易する事もあります。
先日も、このような連載記事を臆面もなく掲載していました。
【デフレの恐怖】(下)日本経済は「低体温症」 頼みは構造改革と成長戦略
(前略)
■続く物価下落
「日本経済が陥っている状況は、まさに低体温症だ」と話すのは、日本総合研究所の湯元健治理事だ。
経済で体温と形容される物価は、このところ下落を続けている。9月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比2・3%の下落で、7カ月連続の前年割れだ。
「先進国では2~3%成長するのが平熱だが、日本はせいぜい1~2%で、悪ければマイナスになる。現状では恒常的な物価下落の状況にあるうえ、慢性的な低成長と税収の縮小に見舞われている。いずれも低体温症によるものだ」(湯元氏)
政策を実行するための資金を確保しようとしても税収が不足している。それをカバーするために国債を増発すれば、償還負担が重くなる。その結果、低成長に至る。デフレという名の低体温症はこの悪循環を慢性化させる。

10月30日に日本銀行が公表した「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」も、日本の潜在成長率を「0%台半ば」とした。景気後退でモノが売れず、企業の設備投資が伸び悩んだためで、4月時点の「1%前後」から下方修正した。
■脱出策は市場拡大
脱出策はあるのか。
湯元氏は「先行きの成長を期待させる政策があれば脱出可能だ」と話す。そのひとつが、小泉内閣で着手した「官から民へ」「中央から地方へ」「貯蓄から投資へ」など構造改革の徹底だ。「国のムダを省き効率的にすることから展望が開ける」と指摘する。
また国内の市場縮小の底流にある人口減少に対応するため、「外国人労働者の導入も本気で検討する必要がある」という。
関西大大学院会計研究科の宮本勝浩教授も市場拡大策を練るべきだと話す。「民主党政権が掲げる富の再配分は重要だが、成長産業を後押しする規制緩和を集中的に進めるなど、経済の成長戦略がなければ低体温症から抜け出すのは難しい。金融政策も重要だ」と指摘する。
大手メーカー幹部は「多くの輸出企業は円高リスクに対応するため体質強化を続けてきた。日本政府が慢性的なデフレへの対策を怠れば、企業は海外に出ていくしかない」と話す。そのうえで、こう言い切った。
「政策はいろいろと検討の余地があるだろう。しかしもっとも大事なのは、低体温症から抜け出す、という固い意志だ」
(MSN産経ニュースより転載)
日本経済が低体温症に陥っているという状況認識は、まあ良いとして、
>国債を増発すれば、償還負担が重くなる。その結果、低成長に至る。
という論理展開は、はっきり言って滅茶苦茶です。
そもそも、償還負担云々と書いている時点で、国の債務と個人や私企業の債務の区別が全くついていません。
三橋貴明氏や廣宮孝信氏の書籍・ブログをほんの少しでも読んだ事がある人なら、もうお分かりのように、現在の日本国国債は100%円建てであり、外貨建てではありません。そのメリットは、何と言っても延々と繰り延べ(ロールオーバー)出来る点にあります。
つまり、償還負担が重くなる事など、経済成長する限り、これっぽっちも起こらないのです。
さらに、国債増発(財政出動)→償還負担が重くなる→低成長という流れは、全くもってワケワカメです。普通なら、国債増発(財政出動)→GDPが持ち直す→経済成長となるのではないでしょうか?
それなのに、景気対策で財政出動しておきながら、どうして低成長(≒不景気)となるのか、論理が飛躍しすぎていて、付いていけません。
思うに、この行燈記事を書いた記者は、
民主党政権は嫌だ!→鳩山内閣がする事なす事全て批判してやれ→「平成22年度当初予算95兆円」は格好の標的→「民主党政権で財政破綻」キャンペーン
という思考回路となっているのではないでしょうか?
こんな脳内フィルターをかけて記事を書くなら、「自民党政権で財政破綻」キャンペーンの朝日新聞と何ら変わりがありません。
そして、挙句の果てに、
「デフレスパイラルから抜け出すために、”官から民へ””中央から地方へ””貯蓄から投資へ”など構造改革を徹底しろ!」
とホザきます。
なまくらは、この竹中式思考回路に茫然自失してしまったので、反論は三橋さんにしていただくことにします。↓
「主問題経済下(三橋注:通常経済下)においては、リカードの比較優位説が作動し、貿易が正当化され、グローバリゼーションが正しい政策になります。このときは、グローバリゼーションにより全てのプレーヤーが豊かになります。
一方、双対問題経済下(三橋注:恐慌経済下)においては、リカードの比較優位説は作動せず、貿易は正当化されず、鎖国が正しい政策になります。このときグローバリゼーションを行えば、すべてのプレーヤーが貧しくなります。(経済学はなぜ間違えるのか P146)」
(中略)
「いや。このまま自由貿易を続け、グローバリゼーションを推し進めれば、あなた方の問題はきっと解決します」
などと言えるはずがありません。自由貿易を続けても、中国などからどんどん安い製品が入ってくるだけで、国内の雇用環境は確実に悪化します。
もちろん、アメリカ政府は財政出動を行い、国内の景気の下支えをしようとするでしょう。しかし、政府が「国民のお金(あえて血税とは書きませんが)」を使い、国内に需要を作り出したとして、自由貿易を続けると、折角苦労して創出した需要を海外諸国に奪われる(輸入増、という形で)結果になってしまうのです。輸入とは、その国のGDPの「控除項目」です。輸入が一方的に増えれば、GDPがその分だけ減少し、国内の需要が奪われてしまいます。
はい。重要な部分なので、しつこく書きます。
「輸入とは、自国の需要を他国に奪われることです。そして輸出とは、他国の需要を奪い取る行為なのです」
(中略)
アメリカの場合は(日本もですが)、ここに「グローバル化されてしまった金融」という問題が加わります。すなわち、上記の読売の記事に登場した人々を助けようと、政府が国内にお金を大量に供給しても、それが金融のグローバルプレーヤー(要はウォール街)により、海外投資に持ち出されてしまうという問題です。
(中略)
グローバル化の進展は、通常経済のフェーズでは有利に働きますが、恐慌経済下では国内の雇用や需要が奪われ、不利に働きます。実践主義の戦略家ぞろいのアメリカが、この事実に気がついていないはずがありません(と言うか、政府首脳部が気がつかずとも、議員は気がつきます)。そろそろ表立って「保護主義」の議論が始まるのではないかなあ、と、予感がしています。
(新世紀のビッグブラザーへBlog「グローバリズムの罠 その1 その2」より一部転載)
構造改革路線が目指す先にはクローバリズムがあるので、産経への批判は上記ブログで既に行われている事がお分かりいただけたでしょうか?
その前にも、
今年、様々な新聞関係者とお会いしましたが、誰もが口をそろえたように、
「産経新聞は名前に『経済』が入っているが、おそらく最も経済について無知な新聞社だ」
と言うのも無理もありません。(但し、面白いことに、皆必ず「田村秀男さんは除くが・・・」と付け加えるのです)
とありましたが、思わず「確かに」と頷いてしまいました。
産経新聞よ、折角、外交・安全保障面で素晴らしい記事を書くのだから、そっちに注力して、経済・財政問題は担当をリストラして田村秀男さん一人に任せてしまいなさい。
そうした方が、きっと早く業績回復できますから。
2009年11月14日
財政は”発散”させろ!
先ほど、「人気ブログランキング(政治)」を覗いてきたら、なんと、三橋氏のブログ「新世紀のビッグブラザーへ」が老舗ブログ「博士の独り言」を抜いて1位になっていました!
書籍の出版や対談など、ここ半年ほど精力的に活動して、知名度が上がってきた効果でしょうか?
なまくらは「博士~」も「新世紀~」もどちらも応援しているので、複雑な気持ちですが・・・
さて、三橋氏と言えば、徹底したソース主義を自認し、また、経済面においては「積極財政派」に分類される方でしょう。
氏は国民をミスリードし、不況を深刻化させる「財政破綻論者」を徹底的にこき下ろしています。特に、マスコミに対しては、厳しい口調で断罪しています。
昨日のエントリーでも、
産経は「経済が全く分かっていない」のですから、この手(国の債務残高を国民一人当たり○○円の借金、と言いかえる論調)のゴミ記事を書いて国民をミスリードするのは、いい加減に止めて欲しいと思うのです。
と一刀両断。
ただ、そんな行灯記事を書いた翌日に別の論者がそれを批判する記事を書いてたりするのが、産経の面白いというか、変わったところでして・・・
一例を挙げますと、
マスコミの経済報道の水準にいたっては教科書のレベルにすら届いていない。例えば国家財政をまったく質の異なる家計に喩(たと)えて「わかりやすく」説明するような愚が繰り返されている。
こうしてミスリードされた「世間知」に基づいて財政問題の議論がなされ、やがて投票行動まで左右していくとなると、もはや収拾がつかない。
(「【40×40】宮崎哲弥 経済学者は役に立っているか?」 より一部転載)
などと平気で書いています。自らの記事を自ら(この場合は外部の人間だが)が否定している訳で、産経はホントに校閲とかしているんでしょうかね?
さて、上記例はまだましな方で、編集委員の田村秀男氏は「国民一人当たり○○円の借金」と書いた記者を背中からバッサリ切りつけています。
【日曜経済講座】編集委員・田村秀男 金融をフル稼働させよ
平成22年度予算の概算要求が、過去最高の95兆円に膨らんだ。さっそく「財源問題」が最大の焦点であるかのように浮上しているが、成長なくして財源見通しは立たない。問われるのは大枠の数字でも帳尻合わせでもなく、日本を新しい成長軌道に乗せる政治の決意である。
(中略)
公共投資や社会保障費の削減、実質的な所得税増税など、緊縮財政がデフレを助長した。以来、GDPの実額は縮小し、税収は減り続け、政府債務が膨れるという悪循環が続いている。
主要国では類をみない日本の超長期デフレ病は、人間の低体温症のように、元気を次第になくさせる。社会格差の広がりと閉塞(へいそく)感はデフレの産物でもある。
(中略)
デフレ本家の日本だけが財政に固執し、世界の主要中央銀行のなかで日銀だけが資金供給を増やそうとしない、
(中略)
そこでカネを動員、または創出して有効需要(カネの裏付けのある需要)を喚起し、雇用の場を創出して、経済のパイを拡大再生産の軌道に乗せることが、政府と中央銀行の役割のはずである。
田村氏の主張は、まんま三橋氏の主張どおりなのが、お分かりいただけたでしょうか?
本来であれば、産経新聞の社説である「主張」も、その他の記事も、田村氏と同意見に落ち着かなくては、新聞としての統一がとれないと思うのですが、この記事が出た後も、相変わらず「95兆円がどうしたこうした」とかいう記事を垂れ流し続けており、訳が分かりません。
さて、田村氏と三橋氏、共に
「GDPを増やして公的債務を発散させろ」
と主張されています。
つまり、公的債務が増え続けても、GDPがそれを上回るペースで増えていけば、公的債務対GDP比率は改善され、そのうち誰も問題視しなくなる、というわけです。
GDPが増えることは、すなわち国民所得が増えることを意味しており、おのずと税収も増え、社会保障費や民主党の大好きな子供手当などの所得再配分政策を行っても十分おつりがくることになります。
ただし、滅多やたらに財政出動しても、経済を成長路線に乗せられなければ、あまり意味がありません。
では、経済を成長させるような財政出動とは、具体的に何でしょうか?両氏は次のように答えています。
・低炭素社会実現に向けた事業(太陽光発電、電気自動車など)
・国民生活を「新たなステージ」に導く支出(リニア新幹線、ITSなど)
・もともと競争力の高かったコンテンツ産業
(「ジパング再来」 三橋貴明著(講談社)より抜粋して引用)
・新規雇用、新ビジネス機会、生活空間を創造するための財政支出
・子育て支援、高速道路無償化など、掲げた政権公約をばらばらに実行するのではなく、「デフレ克服」という太い軸に巻き付ける。
・環境投資、環境に優しい住宅のための投資を促す
・地方独自の自主的な計画でより効率的で利便性や地域産業を活性化させるプロジェクト
・食の安全に見合う農業生産を担う専業農家や農業ビジネスを拡大
・「デフレ克服と生活支援」を同時に達成する政策提案を幅広く民間や地方から募集
(上記記事内「握る6つのポイント」より抜粋して引用)
田村氏の提言の方が、一般論的で具体像に乏しいですが、何かに遠慮しているのでしょうか?
共通項としては、環境面への投資ですね。あとは三橋氏が2ちゃんねる出身作家だけに、コンテンツ産業を挙げ、田村氏が農業ビジネスを挙げたことが興味深かったところです。
なまくらとしては、中国のレアメタル、レアアース囲い込みに対抗した、いわゆる「都市鉱山」の体系的な整備だとか、メタンハイドレートの効率的な採掘法の確立と利用、あるいは介護、農林業等、重労働且つ慢性的な人手不足分野で活躍できるロボットの開発、などを挙げたいと思います。
そして、国民が(陳腐なフレーズですが)安全安心な生活を営むことができるよう、もっと国防予算を増やすべきだと思います。それが何よりの”公共事業”なのかも知れません。
書籍の出版や対談など、ここ半年ほど精力的に活動して、知名度が上がってきた効果でしょうか?
なまくらは「博士~」も「新世紀~」もどちらも応援しているので、複雑な気持ちですが・・・
さて、三橋氏と言えば、徹底したソース主義を自認し、また、経済面においては「積極財政派」に分類される方でしょう。
氏は国民をミスリードし、不況を深刻化させる「財政破綻論者」を徹底的にこき下ろしています。特に、マスコミに対しては、厳しい口調で断罪しています。
昨日のエントリーでも、
産経は「経済が全く分かっていない」のですから、この手(国の債務残高を国民一人当たり○○円の借金、と言いかえる論調)のゴミ記事を書いて国民をミスリードするのは、いい加減に止めて欲しいと思うのです。
と一刀両断。
ただ、そんな行灯記事を書いた翌日に別の論者がそれを批判する記事を書いてたりするのが、産経の面白いというか、変わったところでして・・・
一例を挙げますと、
マスコミの経済報道の水準にいたっては教科書のレベルにすら届いていない。例えば国家財政をまったく質の異なる家計に喩(たと)えて「わかりやすく」説明するような愚が繰り返されている。
こうしてミスリードされた「世間知」に基づいて財政問題の議論がなされ、やがて投票行動まで左右していくとなると、もはや収拾がつかない。
(「【40×40】宮崎哲弥 経済学者は役に立っているか?」 より一部転載)
などと平気で書いています。自らの記事を自ら(この場合は外部の人間だが)が否定している訳で、産経はホントに校閲とかしているんでしょうかね?
さて、上記例はまだましな方で、編集委員の田村秀男氏は「国民一人当たり○○円の借金」と書いた記者を背中からバッサリ切りつけています。
【日曜経済講座】編集委員・田村秀男 金融をフル稼働させよ
平成22年度予算の概算要求が、過去最高の95兆円に膨らんだ。さっそく「財源問題」が最大の焦点であるかのように浮上しているが、成長なくして財源見通しは立たない。問われるのは大枠の数字でも帳尻合わせでもなく、日本を新しい成長軌道に乗せる政治の決意である。
(中略)
公共投資や社会保障費の削減、実質的な所得税増税など、緊縮財政がデフレを助長した。以来、GDPの実額は縮小し、税収は減り続け、政府債務が膨れるという悪循環が続いている。
主要国では類をみない日本の超長期デフレ病は、人間の低体温症のように、元気を次第になくさせる。社会格差の広がりと閉塞(へいそく)感はデフレの産物でもある。
(中略)
デフレ本家の日本だけが財政に固執し、世界の主要中央銀行のなかで日銀だけが資金供給を増やそうとしない、
(中略)
そこでカネを動員、または創出して有効需要(カネの裏付けのある需要)を喚起し、雇用の場を創出して、経済のパイを拡大再生産の軌道に乗せることが、政府と中央銀行の役割のはずである。
田村氏の主張は、まんま三橋氏の主張どおりなのが、お分かりいただけたでしょうか?
本来であれば、産経新聞の社説である「主張」も、その他の記事も、田村氏と同意見に落ち着かなくては、新聞としての統一がとれないと思うのですが、この記事が出た後も、相変わらず「95兆円がどうしたこうした」とかいう記事を垂れ流し続けており、訳が分かりません。
さて、田村氏と三橋氏、共に
「GDPを増やして公的債務を発散させろ」
と主張されています。
つまり、公的債務が増え続けても、GDPがそれを上回るペースで増えていけば、公的債務対GDP比率は改善され、そのうち誰も問題視しなくなる、というわけです。
GDPが増えることは、すなわち国民所得が増えることを意味しており、おのずと税収も増え、社会保障費や民主党の大好きな子供手当などの所得再配分政策を行っても十分おつりがくることになります。
ただし、滅多やたらに財政出動しても、経済を成長路線に乗せられなければ、あまり意味がありません。
では、経済を成長させるような財政出動とは、具体的に何でしょうか?両氏は次のように答えています。
・低炭素社会実現に向けた事業(太陽光発電、電気自動車など)
・国民生活を「新たなステージ」に導く支出(リニア新幹線、ITSなど)
・もともと競争力の高かったコンテンツ産業
(「ジパング再来」 三橋貴明著(講談社)より抜粋して引用)
・新規雇用、新ビジネス機会、生活空間を創造するための財政支出
・子育て支援、高速道路無償化など、掲げた政権公約をばらばらに実行するのではなく、「デフレ克服」という太い軸に巻き付ける。
・環境投資、環境に優しい住宅のための投資を促す
・地方独自の自主的な計画でより効率的で利便性や地域産業を活性化させるプロジェクト
・食の安全に見合う農業生産を担う専業農家や農業ビジネスを拡大
・「デフレ克服と生活支援」を同時に達成する政策提案を幅広く民間や地方から募集
(上記記事内「握る6つのポイント」より抜粋して引用)
田村氏の提言の方が、一般論的で具体像に乏しいですが、何かに遠慮しているのでしょうか?
共通項としては、環境面への投資ですね。あとは三橋氏が2ちゃんねる出身作家だけに、コンテンツ産業を挙げ、田村氏が農業ビジネスを挙げたことが興味深かったところです。
なまくらとしては、中国のレアメタル、レアアース囲い込みに対抗した、いわゆる「都市鉱山」の体系的な整備だとか、メタンハイドレートの効率的な採掘法の確立と利用、あるいは介護、農林業等、重労働且つ慢性的な人手不足分野で活躍できるロボットの開発、などを挙げたいと思います。
そして、国民が(陳腐なフレーズですが)安全安心な生活を営むことができるよう、もっと国防予算を増やすべきだと思います。それが何よりの”公共事業”なのかも知れません。
2009年11月03日
貧困の意味を理解もしない、説明もしないマスゴミと閣僚2
3日前のエントリーに、ゆうくんパパ様からコメント(質問)を頂きました。
回答が長くなるのと、データを示す必要性から、記事の形で回答させていただきます。
ゆうくんパパ様のコメントは、以下のようなものでした。
貧困率は、おっしゃるように、いろいろの限界を持った「相対的な数値」でしかありません。だから、これだけで貧困や経済格差の状況を判断できないのは、当然です。しかし、これを軽視することも、誤りです。
(中略)
>日本より貧困率上位のメキシコ、トルコ、アメリカは、日本より所得格差が大きいと思います。日本のような「所得格差が小さいために貧困率が高い国」って、ほかにどこの国があるのでしょうか?他にも、そういう国がいくつもあるのでなければ、説明にはなりません。
(中略)
>日本の相対的貧困率は、2000年頃から2000年代半ば、つまり小泉政権下に低下しているたしかに、これは貧困者が減ったからではなく、中間層の所得が激減したために、貧困率の「見かけの改善」が起こったのです。このように、貧困率は「相対的」なものであるのはたしかです。しかし、中間層の所得低下は、2003年だけのことでなく、97年からずっと続いていることです。それにもかかわらず、貧困率は増えている。つまり、貧困層の所得はもっと落ちているのです。「絶対的貧困」とは違いますが、少なくとも「貧困の絶対的増加」といっていいと思います。 貧困率を問題にしたからといって「社会主義だ」とかいって批判するのは、それこそ、ものごとの区別がついていないと笑われますよ。
最初の問いは、SAPIO記事から引用した部分についてですね。
できれば引用元に言って欲しい気もしますが…気になって調べたので、お答えします。
OECDが調査した相対的貧困率のデータは、全部で30カ国ありました。ここで日本の最新の相対的貧困率(mid-2000sの欄)は14.9%、概ね14%以上の国を抽出したところ、8カ国ありました。
次に所得格差ですが、まず、所得格差の指標にも色々ありますが、ここでは“ジニ係数”、”国連貧富比”を用いることとしましょう。
ジニ係数は、0に近いほど格差が少ない状態で、1に近いほど格差が大きい状態であることを意味します。
ここでは、0.3以下の国を抽出したところ、10カ国ありました。
国連貧富比は、全世帯を所得の大きさで10ないし5階級に分類したときの、最富裕層と最貧困層の所得比(階層ごとの中央値所得)です。
ここでは、貧富比10%の欄で10以下の国を、20%の欄で5以下の国を抽出し、それぞれ18カ国と12カ国ありました。
結果、これだけでは相関関係が見えてきませんでした。
つまり、所得格差が小さく、相対的貧困率も低い国もあるし、逆に所得格差が大きくても相対的貧困率が小さい国もあったのです。
引用元にある増田氏が、どのような資料を揃えたのかは分かりませんが、日本は高度成長期から現在に至るまで、人口動態が大きく変化している上、北欧諸国などと比べ、世代間格差が大きいため、同世代での格差なども比較しないと、相関関係が見えてこないのかもしれません。
結論としては、強いて言えば、アイルランド、韓国、ポーランドが「所得格差が小さいために貧困率が高い国」となりましたが、ちょっと説得力に欠けますね。今後、新しい資料を見つけたらUPさせていただきます。
(一覧表は後日公開します。)
公開しました。↓

次の問いには、どうお答えしたら良いのか…
「小泉政権時には中間層の所得が低下し、同時に相対的貧困率も低下しているが、押し並べると中間層の所得低下に伴って相対的貧困率は上昇している」
ということですね?で、それは貧困層の所得が中間層の低下より激しく落ちているからだ、と。
↓を見て下さい。

(引用元:http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4663.html)
低所得層の年収は94年をピークに右肩下がりになっていますが、01年頃からほぼ下げ止まっていることが分かります。
一方、所得格差の推移グラフは05年以降、上昇しています。
つまり、貧困層の所得低下ではなく、高所得層、もしくは中間層以上の層で年収上昇が起きているため、相対的貧困率が上昇しているもの、と読み取れそうです。
ゆうくんパパ様が、どこからデータを持ち出して「貧困層の所得が中間層の低下より激しく落ちているから、(相対的)貧困率が増えている」とおっしゃるのかは不明ですが、わたしの収集したデータでは、そのような関係は見受けられませんでした。
もしよろしければ、根拠を示していただけますか?
また、「絶対的貧困とは違う」と言いつつ、「少なくとも『貧困の絶対的増加』といっていいと思う」とは、どういう意味でしょうか?どうも、衣食などにも困る「絶対的貧困」と、統計上の「貧困」を混同なさっている風に見受けられますが、いかがでしょうか?
>貧困率を問題にしたからといって「社会主義だ」とかいって批判するのは
別に政府が貧困率をとりあげた事を問題視するつもりはありません。
そうではなく、マスコミや政府自身が数字が意味するところを理解しようともせず、国民向けの説明もしないまま、「(相対的)貧困率が上昇を続けている!これは旧政権の悪政が原因だ!やっぱり政権交代は正しかった!」などと言わんばかりの姿勢であることを批判しているのです。
また、このデータを根拠に、子ども手当などの所得再配分政策を強化しようとしていますよね?
所得再配分政策が悪い、とまでは言いませんが、不景気の出口が見えない現状で、景気対策(パイの拡大)より所得再配分政策(パイの分配)を優先するのは、間違っていると断定します。
旧社会主義国は、強権を使って富裕層から富を奪い、労働者に分け与えました。
(一部党員を除き)平等にはなりましたが、結果として国富は遅々として増えず、西側陣営に水をあけられる結果となったのは、周知の通りです。
日本は97年以降、一時期を除いてGDPは低下傾向にあります。その中で、パイ(GDP)拡大より分配を優先するなら、手にするパイも年々小さくなるのは明らかでしょう。
今、民主党政権がやろうとしているのは、まさにそういう事で、これは旧社会主義国のやり方に通じる部分があるのです。だから、「みんな貧乏で平等な社会主義国を目指」している、と批判したのです。
(あと、国民の言論の自由を奪おうとしているのも、社会主義国的ですよね)
回答が長くなるのと、データを示す必要性から、記事の形で回答させていただきます。
ゆうくんパパ様のコメントは、以下のようなものでした。
貧困率は、おっしゃるように、いろいろの限界を持った「相対的な数値」でしかありません。だから、これだけで貧困や経済格差の状況を判断できないのは、当然です。しかし、これを軽視することも、誤りです。
(中略)
>日本より貧困率上位のメキシコ、トルコ、アメリカは、日本より所得格差が大きいと思います。日本のような「所得格差が小さいために貧困率が高い国」って、ほかにどこの国があるのでしょうか?他にも、そういう国がいくつもあるのでなければ、説明にはなりません。
(中略)
>日本の相対的貧困率は、2000年頃から2000年代半ば、つまり小泉政権下に低下しているたしかに、これは貧困者が減ったからではなく、中間層の所得が激減したために、貧困率の「見かけの改善」が起こったのです。このように、貧困率は「相対的」なものであるのはたしかです。しかし、中間層の所得低下は、2003年だけのことでなく、97年からずっと続いていることです。それにもかかわらず、貧困率は増えている。つまり、貧困層の所得はもっと落ちているのです。「絶対的貧困」とは違いますが、少なくとも「貧困の絶対的増加」といっていいと思います。 貧困率を問題にしたからといって「社会主義だ」とかいって批判するのは、それこそ、ものごとの区別がついていないと笑われますよ。
最初の問いは、SAPIO記事から引用した部分についてですね。
できれば引用元に言って欲しい気もしますが…気になって調べたので、お答えします。
OECDが調査した相対的貧困率のデータは、全部で30カ国ありました。ここで日本の最新の相対的貧困率(mid-2000sの欄)は14.9%、概ね14%以上の国を抽出したところ、8カ国ありました。
次に所得格差ですが、まず、所得格差の指標にも色々ありますが、ここでは“ジニ係数”、”国連貧富比”を用いることとしましょう。
ジニ係数は、0に近いほど格差が少ない状態で、1に近いほど格差が大きい状態であることを意味します。
ここでは、0.3以下の国を抽出したところ、10カ国ありました。
国連貧富比は、全世帯を所得の大きさで10ないし5階級に分類したときの、最富裕層と最貧困層の所得比(階層ごとの中央値所得)です。
ここでは、貧富比10%の欄で10以下の国を、20%の欄で5以下の国を抽出し、それぞれ18カ国と12カ国ありました。
結果、これだけでは相関関係が見えてきませんでした。
つまり、所得格差が小さく、相対的貧困率も低い国もあるし、逆に所得格差が大きくても相対的貧困率が小さい国もあったのです。
引用元にある増田氏が、どのような資料を揃えたのかは分かりませんが、日本は高度成長期から現在に至るまで、人口動態が大きく変化している上、北欧諸国などと比べ、世代間格差が大きいため、同世代での格差なども比較しないと、相関関係が見えてこないのかもしれません。
結論としては、強いて言えば、アイルランド、韓国、ポーランドが「所得格差が小さいために貧困率が高い国」となりましたが、ちょっと説得力に欠けますね。今後、新しい資料を見つけたらUPさせていただきます。
公開しました。↓

次の問いには、どうお答えしたら良いのか…
「小泉政権時には中間層の所得が低下し、同時に相対的貧困率も低下しているが、押し並べると中間層の所得低下に伴って相対的貧困率は上昇している」
ということですね?で、それは貧困層の所得が中間層の低下より激しく落ちているからだ、と。
↓を見て下さい。

(引用元:http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4663.html)
低所得層の年収は94年をピークに右肩下がりになっていますが、01年頃からほぼ下げ止まっていることが分かります。
一方、所得格差の推移グラフは05年以降、上昇しています。
つまり、貧困層の所得低下ではなく、高所得層、もしくは中間層以上の層で年収上昇が起きているため、相対的貧困率が上昇しているもの、と読み取れそうです。
ゆうくんパパ様が、どこからデータを持ち出して「貧困層の所得が中間層の低下より激しく落ちているから、(相対的)貧困率が増えている」とおっしゃるのかは不明ですが、わたしの収集したデータでは、そのような関係は見受けられませんでした。
もしよろしければ、根拠を示していただけますか?
また、「絶対的貧困とは違う」と言いつつ、「少なくとも『貧困の絶対的増加』といっていいと思う」とは、どういう意味でしょうか?どうも、衣食などにも困る「絶対的貧困」と、統計上の「貧困」を混同なさっている風に見受けられますが、いかがでしょうか?
>貧困率を問題にしたからといって「社会主義だ」とかいって批判するのは
別に政府が貧困率をとりあげた事を問題視するつもりはありません。
そうではなく、マスコミや政府自身が数字が意味するところを理解しようともせず、国民向けの説明もしないまま、「(相対的)貧困率が上昇を続けている!これは旧政権の悪政が原因だ!やっぱり政権交代は正しかった!」などと言わんばかりの姿勢であることを批判しているのです。
また、このデータを根拠に、子ども手当などの所得再配分政策を強化しようとしていますよね?
所得再配分政策が悪い、とまでは言いませんが、不景気の出口が見えない現状で、景気対策(パイの拡大)より所得再配分政策(パイの分配)を優先するのは、間違っていると断定します。
旧社会主義国は、強権を使って富裕層から富を奪い、労働者に分け与えました。
(一部党員を除き)平等にはなりましたが、結果として国富は遅々として増えず、西側陣営に水をあけられる結果となったのは、周知の通りです。
日本は97年以降、一時期を除いてGDPは低下傾向にあります。その中で、パイ(GDP)拡大より分配を優先するなら、手にするパイも年々小さくなるのは明らかでしょう。
今、民主党政権がやろうとしているのは、まさにそういう事で、これは旧社会主義国のやり方に通じる部分があるのです。だから、「みんな貧乏で平等な社会主義国を目指」している、と批判したのです。
(あと、国民の言論の自由を奪おうとしているのも、社会主義国的ですよね)
2009年11月01日
足元の問題を放置するのがお得意!?な人々
「最近、本当に洋服が安くなったとおもいませんか?」
の武坊さんの一言で始まった、先々週のGO!GO!NEWSです。
相次ぐ激安品にジーンズ業界悲鳴 顧客離れ加速 製造は中国 恩恵なく
ジーンズ業界が、総合スーパーなどによる激安品の相次ぐ発売に悲鳴を上げている。低価格志向を強める消費者が飛びつき、顧客離れが加速しているためだ。ジーンズメーカーや、ジーンズを主力商品とする衣料品販売会社は、軒並み業績を悪化させている。
「リーバイス」ブランドを展開するリーバイ・ストラウス・ジャパンが今月発表した平成21年11月期決算の第3四半期までの累計は、売上高が前年同期比19・7%減の約132億円と大きく落ち込んだ。
カジュアル衣料販売大手のジーンズメイトも先月、平成22年2月期の連結営業損益見通しを従来予想の2000万円の黒字から3億9000万円の赤字に下方修正した。ジーンズメイトの福井三紀夫社長は「激安品に顧客を食われた」と肩を落とす。
深刻な販売不振を受け、事業縮小の動きも出ている。国内メーカー大手のボブソン(岡山市)は月内にも、「ボブソン」ブランドを企業再生会社に譲渡し、子 供服の製造販売に事業を絞る。影響は素材分野にも及び、クラボウはデニム生地の糸を生産する岡山工場を6月末に閉鎖した。
ジーンズの“価格破壊”を最初に仕掛けたのは、カジュアル衣料店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングだ。3月に、傘下のユニクロ姉妹店「ジー ユー」から990円のプライベートブランド(PB、自主企画)商品を発売した。これに、イオンなど総合スーパー各社が追随し、今月14日には、ディスカウント販売大手のドン・キホーテも最安値となる690円のPB商品を売り出した。
各社とも大半の商品の製造を人件費の安い中国企業に委託しており、国内メーカーはほとんど恩恵を受けていない。激安品への対抗策として、ジーンズメイトは自らPB商品の発売を検討しているが、価格競争に巻き込まれる懸念はぬぐえない。若者のジーンズ離れもあり、「(販売回復の)特効薬が見当たらない」(福井社長)と、専業メーカーは苦悩を深めている。
(MSN産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/economy/business/091017/biz0910172233009-n1.htmより、GO!GO!NEWSも、そのまま引用したもよう)
武坊
今日の結論から言うと、極端な安さは大きな罪だ、と言いたいですね。
モノの値段は元々、原価+利潤=値段 ですけれども、値段を下げていくには、どちらかを下げないといけないですよね。で、利潤を下げちゃうと株主への配当なども滞るから、ここはある程度確保しないといけない、となるとやはりコスト削減という方向に行くんですよね。
で、いきおい海外での生産、てことになっていましたけれども、国内の雇用が悲鳴を上げているってことですよね。失業者はバンバン出ますわね。
さらに、もっと根深い問題がありまして、じゃあ、中国やベトナムといった受注している国はウハウハか?、というと、実はそうじゃない、てのを見つけてきたのでご紹介します。
一時期は中国が多かったですわ。でも今はベトナム、モロッコ、マレーシア…
つまり、人件費の安い国同士が、日本から受注するために、人件費の値下げ合戦になっている、というんですよ。
で、どうやって下げるか、と言いますと、どの国でもやっぱり大の大人を雇うと賃金高いらしいんですね。だから、大人の男のクビを切って女性に働かせる、と。すると、安く済む。
で、別の国がもっと安い人件費でセールスかけてきたら、
「じゃあ、ちょっと待て、女もクビ切れ、子供を雇え。」
てことになる。12,3歳の子供に、技術は教えませんよ。縫製マニュアルだけ与えて12時間とか15時間労働という非常に過酷な労働を強いていて、だからこれだけコストが安くあがってきている、という現状があるんですね。
ILO(国際労働機関)は人権上、どんな発展途上国でも児童の労働は禁止しているんです。
でも、抜け道があるんです。
聞いたことないですか?経済特区、てやつ。別の言い方だと、自由通商地帯、て言うんですか?
元々は、工業団地みたいなものだったですよね。
「外国企業の皆さん、インフラ整備していますから、どうぞ来てください、で、ここに工場作ってくれたら、ウチの国の法律のこの部分とこの部分は適用しませんよ。環境に関しては、あまり。労働条件に関やかましいこと言いませんよしても、やかましいこと言いませんよ。」
だから、ああいう発展途上国からしてみれば、先進国の仕事を請け負うためには、もう非合法なものも合法的にしてしまおう、と特区を作ってしまう。
こうなると、法律の網はかけられない、やりたい放題なわけですよ。
で、そういう生産・販売システムの中で巨額の富を得てきたのが、もうこれ、改善したから言いますけど、ナイキ、アディダス、ギャップといったところが数年前、アメリカですっごく叩きまわされたんです。
「あれだけ安く作っていたのにも関わらず、何でエアーナイキが1万5千円もするんだ!」
なんて叩きまわされたことがありました。
アディダスとギャップは早々と認めて改善しましたけれども、ナイキは最初の方は
「いや、私どもはそういう指導はしておりません。」
とか言っていたけれども、やっぱり数年後、あまりにもバッシングが酷くて、発展途上国での労働条件も見直していくという方向にあります。
さて、じゃあ日本はどうですか?
日本の多国籍企業と言われる繊維業界は、実はそういった同じ構図の中にあります。
だから、皆さんが安いわ、て買っていることが実は、発展途上国の子供達の非常に極貧の上に成り立っている、ていうのが、考えたら怖いことでしょ?
でも、じゃあどうやって企業が環境にも人にも優しい経営をしているのか、て分かんないでしょ?消費者からは。
そこで、アメリカの市民団体が、こういう本を作りました。
「Shopping for a Better World」
これ、どう言ってるかと言うと、皆さんの買い物がより良い世界を導くんですよ、ていう本で、企業をそれぞれ診断しているのよ。
今までムーディーズとかは財務状態だけでAAAとかやっていたでしょ?そうじゃなくて、
淳ちゃん
人権に関わることだとか、エコに関わる事だとか…
武坊
そうそう、それで出版したら、何と100万部以上売れたらしい。
淳ちゃん
興味ありますよね。気になるところではあったんじゃないかな?
だって、消費者だって常識ってものがあるわけで、「何でここまで安くなるの?」て嬉しい半面、疑問は持っていたと思うから。それが分かりやすく説明されていたわけでしょ?
武坊
そうそう、だからこれを買った読者は、少々高くてもこれまでの消費動向が変わった、て言っているらしい。
淳ちゃん
要は、適正価格が分かる、てことだね。
武坊
そういうことだね。是非これを、日本版でやれないかな、て思う。
これは行政が旗振る問題じゃないかもしれないけれども、消費者庁ってものが出来ているし、福島瑞穂さんもいるし、是非「Shopping for a Better World in Japan」みたいなものが出来ないかなぁ、と思って。
今、コンプライアンスだとかCSRだとか言っているけれども、こういったところですよ、まずね。
淳ちゃん
日本人はそして、再生というか、例えば古着、古本などの再生のモノの考え方を持っているわけだから、もう一歩進んだ考え方が出来ると思いますけれどもね。
(以上、書き起こし終わり)
1月ほど前にも、この「Shopping for a Better World」を紹介していましたね。武坊さん、よっぽどこの本がお気に入りのご様子。
で、この本は一体どういったものなのか、ちょっと調べてみました。
30年ほど前、ウォール街で働いていた、アリス・テッパー・マーリンという人がCEP(経済優先順位研究所)という組織を設立し、88年から消費者向けに発行を始めた買い物ガイドらしいです。
CEPは当初、環境汚染について調査していたが、現在は以下の7つの指標で評価しているそうです。
1.環境保護度
有害物質の排出量、環境法の遵守度、環境マネジメントシステムの有無。
2.女性の働きやすさ
女性の地位、数、地位向上のための教育プログラム、女性がオーナーのサプライヤーとの取引の有無。
3.マイノリティの働きやすさ
マイノリティの地位、数、地位向上のための教育プログラム、マイノリティがオーナーのサプライヤーとの取引の有無。
4.寄付行為
お金だけでなく備品、サービスの提供も含んでいる。
5.ファミリー重視度
仕事と家庭が両立するためのプログラム、育児支援、介護支援、フレックスタイムなどの有無。
6.労働環境への配慮度
保険制度、年金、ボーナス、教育制度の有無。労働法の遵守など。
7.情報公開
上記の6 つの情報が公開されているかなど。
(参考:http://blhrri.org/kenkyu/bukai/jinken/kigyo/kigyo_0008.htm )
まあ、アメリカらしく、“マイノリティの働きやすさ”や“寄付行為”なんていうのも指標に入っていますが、基本的に“人と自然に優しい企業の紹介”みたいなものですかね。
同意できる部分も少なからずありますが、これをそのままストレートに日本に持ってきて、「Shopping for a Better World in Japan」みたいなのを作られた日には、ちょっと黙っておけないでしょうね。
だって、歴史的背景などを鑑みずに“マイノリティがオーナーのサプライヤーとの取引の有無”なんていうのが採点基準になると、半島系パチンコ屋との取引がある企業が有利になる、というおかしなことが起きてしまいます。
“人と自然に優しい企業の紹介”なのに、人生を賭博に狂わせ、その上集めた資金を核ミサイルの開発に利用している企業とのつながりがある方が評価が高い、て、矛盾しすぎです。
環境面でも、「うちはCO2を25%減らそうとしている民主党を応援します」と言っただけでプラス評価がされそうだし、寄付行為なんてあまりにも漠然としすぎです。
大元の理念みたいなものは、評価できますが、個別によーく検証してから導入しないと、差別利権や環境利権に群がる人々(左翼系が多い)に食い物にされそうです。
あと、工場が移った先の、発展途上国の労働問題については、フェアトレードっていうシステムもありますが、これもよーく見てみたら、フェアトレードをやっている組織が実は中間搾取を行っていて、労働問題の解決にはほとんど役立っていない、とかありそうです。まあ、あくまで主観の入ったひねくれた推測ですが…
でも、国内のフェアトレード組織を紹介するHPからリンクを辿っていくと、反戦本の紹介もしている組織にぶち当たったり、と、何かと政治臭漂う発見があったのも事実です。
一概に切り捨てて論評するつもりはありませんし、真面目に活動している人だって少なからずいるでしょう。
ただ、無条件に「この人達は良いことをしている」と思ってせっせとそこの商品を買っていても、その思いが届かない可能性があるのは知っておくべきかと思います。
こうなってくると、「発展途上国の子供達の為に」と、せっせとフェアトレードや上記紹介本で紹介された企業の商品を買うよりも、素直に国産の商品を買っておいた方が、後から「裏切られた」なんて思う事も少ないのではないでしょうか?
それに、何といっても、派遣切りなどの雇用問題解決の突破口になるのではないでしょうか。
結局は、先月初めの金美齢先生の小林市での講演会の内容に繋がるんですね。
自国の、もっと言えば地域の問題さえ解決しようとしてないのに、グローバルな問題に目を向けるのって、偽善っぽいというか、順番が違うぞ、と言いたいです。
の武坊さんの一言で始まった、先々週のGO!GO!NEWSです。
相次ぐ激安品にジーンズ業界悲鳴 顧客離れ加速 製造は中国 恩恵なく
ジーンズ業界が、総合スーパーなどによる激安品の相次ぐ発売に悲鳴を上げている。低価格志向を強める消費者が飛びつき、顧客離れが加速しているためだ。ジーンズメーカーや、ジーンズを主力商品とする衣料品販売会社は、軒並み業績を悪化させている。
「リーバイス」ブランドを展開するリーバイ・ストラウス・ジャパンが今月発表した平成21年11月期決算の第3四半期までの累計は、売上高が前年同期比19・7%減の約132億円と大きく落ち込んだ。
カジュアル衣料販売大手のジーンズメイトも先月、平成22年2月期の連結営業損益見通しを従来予想の2000万円の黒字から3億9000万円の赤字に下方修正した。ジーンズメイトの福井三紀夫社長は「激安品に顧客を食われた」と肩を落とす。
深刻な販売不振を受け、事業縮小の動きも出ている。国内メーカー大手のボブソン(岡山市)は月内にも、「ボブソン」ブランドを企業再生会社に譲渡し、子 供服の製造販売に事業を絞る。影響は素材分野にも及び、クラボウはデニム生地の糸を生産する岡山工場を6月末に閉鎖した。
ジーンズの“価格破壊”を最初に仕掛けたのは、カジュアル衣料店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングだ。3月に、傘下のユニクロ姉妹店「ジー ユー」から990円のプライベートブランド(PB、自主企画)商品を発売した。これに、イオンなど総合スーパー各社が追随し、今月14日には、ディスカウント販売大手のドン・キホーテも最安値となる690円のPB商品を売り出した。
各社とも大半の商品の製造を人件費の安い中国企業に委託しており、国内メーカーはほとんど恩恵を受けていない。激安品への対抗策として、ジーンズメイトは自らPB商品の発売を検討しているが、価格競争に巻き込まれる懸念はぬぐえない。若者のジーンズ離れもあり、「(販売回復の)特効薬が見当たらない」(福井社長)と、専業メーカーは苦悩を深めている。
(MSN産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/economy/business/091017/biz0910172233009-n1.htmより、GO!GO!NEWSも、そのまま引用したもよう)
武坊
今日の結論から言うと、極端な安さは大きな罪だ、と言いたいですね。
モノの値段は元々、原価+利潤=値段 ですけれども、値段を下げていくには、どちらかを下げないといけないですよね。で、利潤を下げちゃうと株主への配当なども滞るから、ここはある程度確保しないといけない、となるとやはりコスト削減という方向に行くんですよね。
で、いきおい海外での生産、てことになっていましたけれども、国内の雇用が悲鳴を上げているってことですよね。失業者はバンバン出ますわね。
さらに、もっと根深い問題がありまして、じゃあ、中国やベトナムといった受注している国はウハウハか?、というと、実はそうじゃない、てのを見つけてきたのでご紹介します。
一時期は中国が多かったですわ。でも今はベトナム、モロッコ、マレーシア…
つまり、人件費の安い国同士が、日本から受注するために、人件費の値下げ合戦になっている、というんですよ。
で、どうやって下げるか、と言いますと、どの国でもやっぱり大の大人を雇うと賃金高いらしいんですね。だから、大人の男のクビを切って女性に働かせる、と。すると、安く済む。
で、別の国がもっと安い人件費でセールスかけてきたら、
「じゃあ、ちょっと待て、女もクビ切れ、子供を雇え。」
てことになる。12,3歳の子供に、技術は教えませんよ。縫製マニュアルだけ与えて12時間とか15時間労働という非常に過酷な労働を強いていて、だからこれだけコストが安くあがってきている、という現状があるんですね。
ILO(国際労働機関)は人権上、どんな発展途上国でも児童の労働は禁止しているんです。
でも、抜け道があるんです。
聞いたことないですか?経済特区、てやつ。別の言い方だと、自由通商地帯、て言うんですか?
元々は、工業団地みたいなものだったですよね。
「外国企業の皆さん、インフラ整備していますから、どうぞ来てください、で、ここに工場作ってくれたら、ウチの国の法律のこの部分とこの部分は適用しませんよ。環境に関しては、あまり。労働条件に関やかましいこと言いませんよしても、やかましいこと言いませんよ。」
だから、ああいう発展途上国からしてみれば、先進国の仕事を請け負うためには、もう非合法なものも合法的にしてしまおう、と特区を作ってしまう。
こうなると、法律の網はかけられない、やりたい放題なわけですよ。
で、そういう生産・販売システムの中で巨額の富を得てきたのが、もうこれ、改善したから言いますけど、ナイキ、アディダス、ギャップといったところが数年前、アメリカですっごく叩きまわされたんです。
「あれだけ安く作っていたのにも関わらず、何でエアーナイキが1万5千円もするんだ!」
なんて叩きまわされたことがありました。
アディダスとギャップは早々と認めて改善しましたけれども、ナイキは最初の方は
「いや、私どもはそういう指導はしておりません。」
とか言っていたけれども、やっぱり数年後、あまりにもバッシングが酷くて、発展途上国での労働条件も見直していくという方向にあります。
さて、じゃあ日本はどうですか?
日本の多国籍企業と言われる繊維業界は、実はそういった同じ構図の中にあります。
だから、皆さんが安いわ、て買っていることが実は、発展途上国の子供達の非常に極貧の上に成り立っている、ていうのが、考えたら怖いことでしょ?
でも、じゃあどうやって企業が環境にも人にも優しい経営をしているのか、て分かんないでしょ?消費者からは。
そこで、アメリカの市民団体が、こういう本を作りました。
「Shopping for a Better World」
これ、どう言ってるかと言うと、皆さんの買い物がより良い世界を導くんですよ、ていう本で、企業をそれぞれ診断しているのよ。
今までムーディーズとかは財務状態だけでAAAとかやっていたでしょ?そうじゃなくて、
淳ちゃん
人権に関わることだとか、エコに関わる事だとか…
武坊
そうそう、それで出版したら、何と100万部以上売れたらしい。
淳ちゃん
興味ありますよね。気になるところではあったんじゃないかな?
だって、消費者だって常識ってものがあるわけで、「何でここまで安くなるの?」て嬉しい半面、疑問は持っていたと思うから。それが分かりやすく説明されていたわけでしょ?
武坊
そうそう、だからこれを買った読者は、少々高くてもこれまでの消費動向が変わった、て言っているらしい。
淳ちゃん
要は、適正価格が分かる、てことだね。
武坊
そういうことだね。是非これを、日本版でやれないかな、て思う。
これは行政が旗振る問題じゃないかもしれないけれども、消費者庁ってものが出来ているし、福島瑞穂さんもいるし、是非「Shopping for a Better World in Japan」みたいなものが出来ないかなぁ、と思って。
今、コンプライアンスだとかCSRだとか言っているけれども、こういったところですよ、まずね。
淳ちゃん
日本人はそして、再生というか、例えば古着、古本などの再生のモノの考え方を持っているわけだから、もう一歩進んだ考え方が出来ると思いますけれどもね。
(以上、書き起こし終わり)
1月ほど前にも、この「Shopping for a Better World」を紹介していましたね。武坊さん、よっぽどこの本がお気に入りのご様子。
で、この本は一体どういったものなのか、ちょっと調べてみました。
30年ほど前、ウォール街で働いていた、アリス・テッパー・マーリンという人がCEP(経済優先順位研究所)という組織を設立し、88年から消費者向けに発行を始めた買い物ガイドらしいです。
CEPは当初、環境汚染について調査していたが、現在は以下の7つの指標で評価しているそうです。
1.環境保護度
有害物質の排出量、環境法の遵守度、環境マネジメントシステムの有無。
2.女性の働きやすさ
女性の地位、数、地位向上のための教育プログラム、女性がオーナーのサプライヤーとの取引の有無。
3.マイノリティの働きやすさ
マイノリティの地位、数、地位向上のための教育プログラム、マイノリティがオーナーのサプライヤーとの取引の有無。
4.寄付行為
お金だけでなく備品、サービスの提供も含んでいる。
5.ファミリー重視度
仕事と家庭が両立するためのプログラム、育児支援、介護支援、フレックスタイムなどの有無。
6.労働環境への配慮度
保険制度、年金、ボーナス、教育制度の有無。労働法の遵守など。
7.情報公開
上記の6 つの情報が公開されているかなど。
(参考:http://blhrri.org/kenkyu/bukai/jinken/kigyo/kigyo_0008.htm )
まあ、アメリカらしく、“マイノリティの働きやすさ”や“寄付行為”なんていうのも指標に入っていますが、基本的に“人と自然に優しい企業の紹介”みたいなものですかね。
同意できる部分も少なからずありますが、これをそのままストレートに日本に持ってきて、「Shopping for a Better World in Japan」みたいなのを作られた日には、ちょっと黙っておけないでしょうね。
だって、歴史的背景などを鑑みずに“マイノリティがオーナーのサプライヤーとの取引の有無”なんていうのが採点基準になると、半島系パチンコ屋との取引がある企業が有利になる、というおかしなことが起きてしまいます。
“人と自然に優しい企業の紹介”なのに、人生を賭博に狂わせ、その上集めた資金を核ミサイルの開発に利用している企業とのつながりがある方が評価が高い、て、矛盾しすぎです。
環境面でも、「うちはCO2を25%減らそうとしている民主党を応援します」と言っただけでプラス評価がされそうだし、寄付行為なんてあまりにも漠然としすぎです。
大元の理念みたいなものは、評価できますが、個別によーく検証してから導入しないと、差別利権や環境利権に群がる人々(左翼系が多い)に食い物にされそうです。
あと、工場が移った先の、発展途上国の労働問題については、フェアトレードっていうシステムもありますが、これもよーく見てみたら、フェアトレードをやっている組織が実は中間搾取を行っていて、労働問題の解決にはほとんど役立っていない、とかありそうです。まあ、あくまで主観の入ったひねくれた推測ですが…
でも、国内のフェアトレード組織を紹介するHPからリンクを辿っていくと、反戦本の紹介もしている組織にぶち当たったり、と、何かと政治臭漂う発見があったのも事実です。
一概に切り捨てて論評するつもりはありませんし、真面目に活動している人だって少なからずいるでしょう。
ただ、無条件に「この人達は良いことをしている」と思ってせっせとそこの商品を買っていても、その思いが届かない可能性があるのは知っておくべきかと思います。
こうなってくると、「発展途上国の子供達の為に」と、せっせとフェアトレードや上記紹介本で紹介された企業の商品を買うよりも、素直に国産の商品を買っておいた方が、後から「裏切られた」なんて思う事も少ないのではないでしょうか?
それに、何といっても、派遣切りなどの雇用問題解決の突破口になるのではないでしょうか。
結局は、先月初めの金美齢先生の小林市での講演会の内容に繋がるんですね。
自国の、もっと言えば地域の問題さえ解決しようとしてないのに、グローバルな問題に目を向けるのって、偽善っぽいというか、順番が違うぞ、と言いたいです。
2009年09月26日
地方を殺すな! ~高速無料化時代の地方再生策
今日の話題は、前エントリーも参照していただくと、より分かりやすいです。
また、今日はいつもより長いです。
民主党は衆院選のマニフェスト(政権公約)で明記した「高速道路の無料化」を、北海道と九州で来年度から先行実施する方針を固めた。複数の関係筋が14日、明らかにした。利用状況や経済効果をにらみながら無料化路線を段階的に拡大していく考えだ。
ただ、これまでの道路建設に伴う約30兆円の有利子負債や道路の維持管理コストをどう捻出(ねんしゅつ)するかはいまだに示されていない。民主党の鳩山由紀夫代表が掲げる「温室効果ガス25%削減」方針にも矛盾するとの指摘もある。
無料化を先行実施するのは、供用されている高速道路約7678キロのうち、北海道エリアの581キロ、九州エリアの794キロ。東名高速など大都市圏をつなぐ主要路線と比べると、交通量が少ない路線だ。
高速道路を無料化すれば、交通渋滞、排ガスによる環境悪化、料金所廃止による雇用問題、他の交通機関への影響-など数々の問題が起きるといわれる。
このため、民主党では、交通量が少なく、限定された地域で先行実施すれば、無料化に伴う悪影響を最小限にとどめることができる上、対策を講じやすいと判断した。加えて地域経済に与える効果などを把握でき、このデータを基に複合的な地域活性化策を策定できるメリットもある。
民主党は、マニフェスト工程表で、平成24年度には首都高速、阪神高速を除くすべての高速道路を「原則無料開放」する方針を示した。これに伴い、民主党は23年度の通常国会で、高速道路を保有する独立行政法人「日本高速道路保有・債務返済機構」を国有化するため法改正する方針。無料化後の高速道路は一般国道の「自動車専用道路」とする方向で検討している。
民主党は経済効果を3年間で2兆円、国内総生産(GDP)を0・41%押し上げると試算している。国交省も20年、首都高速と阪神高速を除く無料化による経済効果を2兆7千億円とする試算をまとめた。
一方、国有化すれば、返済機構が抱える約30兆円の有利子負債は国の債務として計上され、道路の維持管理費や新規建設費は税金で負担することになる。
(以上、MSN産経ニュースより引用)
武坊
だから、わたし達の宮崎自動車道、このあたりが全国に先駆けてタダになる可能性があるということですね?で、九州道もでしょ?だから、福岡まで来年度、いよいよタダになるっていうのが見えてきた、ということですよね。
駆け込みでETC付けた皆さん、それ、あんまり意味無くなりますね(笑)
で、高速が0円になった場合、国交省が自動車の年間利用者が57.5%増えるだろう、と見越しております。で、鉄道に乗る人は10.6%減るだろう、飛行機も4.2%減るだろうというような集計結果を明らかにしております。
ま、色んなところに影響があるんですけれども、取りあえず九州が先駆けてタダになる、て言う事は、今まで商圏を宮崎なら宮崎エリア、せいぜい鹿児島エリアまで入れてたかも知れないけれども、平日も土日も含めてタダ、て言う事になると、ちょっと商圏を広げて考えないといけなくなりますよね?
アウトレットモールが鳥栖にあったでしょ?ああいった所もガソリン代だけで行けてしまうわけだから、宮崎の郊外型のショッピングセンター・モールの敵に、いきなりなるわけですよ。200km離れていようが。
片やこっちは定価で売っている、片や3割、4割引きで売っているとなると、そこでもバチバチ火花が散り始める…
淳ちゃん
勉強不足で申し訳ないけれども、建設予定の高速道路があるわけやろ?それ、ちゃんと期間内にできるんやろか?
武坊
それはまだ、はっきり言ってないですよね。
淳ちゃん
きちんと造ってもらわないと困るし、出来ないと、お客さんは逃げて行ってしまう。やっぱりこれは、どうなるんだろう?ちょっと心配かな?
武坊
よく、高速道路はストロー化現象の象徴だ、と言われていて、便利な道を造ると、力のある方が力のない方のお金、人を吸い上げていく、と言われてました。でも今までは福岡まで行くのに普通車で5,6千円という“通行手形”が要ったわけや。それが関所になってたけど、今度はそのストローが本っ当に通りの良いストローになるわけやから、チューと吸おうと思えば吸えるわけで、本当に勝ち負け明暗分かれると思いますよ?ね?
淳ちゃん
ま、その分例えば通勤とかで高速道路を使えるようになることによって、もっと住みやすい場所があるとか、そういうのがあるのかも分からないけど、まあそれ、1,2年ていうわけじゃないやろうからね。
武坊
何でも功罪両面あるんだろうけれども、この高速タダ、ていうのは、“功”の分より“罪”というか痛む分のケア、どうせケアしなきゃいけないやろ?鉄道にしろ、フェリーなんか直ですよね。でもそれを潰すわけにいかないから、それを税金で助けたりするわけでしょ?
ならば、やっぱり0円じゃなくて、整合性取った方が良いようにありますけれどもね。
淳ちゃん
バランス、ということを考えると、この超高齢化社会において、車の運転をしなくなる人、できなくなる人は増えてくるわけでしょ?そういう方々が利用する公共交通機関の料金が、反対に高くなったらどうするんだろう?
で、ちょっと違う話をして良い?
この間、私はタイのバンコクに行きました。福岡からバンコクまで格安航空券を手に入れ、往復3万8千円でした。で、仕事があったので、行き帰りを飛行機で福岡―宮崎間を利用し、往復2万5千円かかりました。分かります?国内路線が日本は高い、と。これは仕方がないだろう、色んな理由があって。にしても、ユーロ圏であっても、国内あるいは陸続きの隣国に行く料金は、やっぱり安いわ。これでお客を乗せて飛行機を飛ばせて、価格も…
どうなんだろうね?この価格差は。
武坊
淳子さんの場合は2万5千円かけて飛行機乗ったけれども、スケジュールさえ合えば、ガソリン代だけで行けたわけでしょ?て事はさ、そこに物凄い差が生まれるから、じゃあ夜中に着く便でも、兎に角無茶してでも車で行こうとする人は増えますわな。
淳ちゃん
でも、人間歳とると無茶できなくなるでしょ?やっぱそこら辺のバランス、ていうのを考えてほしいな、とふと思った48歳でした(笑)
武坊
どうなんだろう?前にもこの番組で言ったけれども、上限5千円くらいで打ち切り、で良いんじゃない?財源確保できて、それで道路造ります、て言えば良いわぁ。0、て言ったらさぁ、ねぇ?
淳ちゃん
で、それで陸・海・空のバランスを少し考えてもらって、色んなところで補助しないといけないんだろうから、もうちょっと使い勝手の良いような交通手段を作って欲しいな、と改めて思いました。
(書き起こし終わり)
ま、一応正論ですね。
高速道路が無料化すれば、ストロー現象がますます激しくなって、地方都市、特に中心市街地がますます衰退する、という武坊さんの予感、多分当たると思います。
そして、最終的には全国10~30のインターチェンジ近郊に10万㎡クラスの超大型モールと、各地方都市ごとにモールの関連小売業者、もっと具体的に言うと、インターにはイオンモール、各都市にはマックスバリュやホームワイドといった店が立ち並ぶことになるでしょう。
今でさえ、地方中核都市の近郊と、それ以外の市町村の関係は、そうなってますよね。これが、全国規模に拡大される、と考えられるわけです。
国民のほとんどが休日を各地のイオンモールで過ごす世の中・・・ちょっと考えただけで、気持ち悪くないですか?
まあ、そこまで極端にならなくても、地方の中心市街地は確実に衰退します。
そして、そこに至る過程で、小売業界は中心市街地、郊外を問わず、熾烈な過当競争に巻き込まれます。
『(前略)最終的には、持久戦に敗れた多くの事業者が撤退し、(中略)上下水道や道路が整った郊外開発地に大量の空き店舗や駐車場の残骸が発生していることになります。その後始末は行政の手をわずらわせ、結局は増税などを通じて住民や地域の企業に転嫁されます。(後略)』
(藻谷 浩介氏著「『焼畑農業』と化した郊外乱開発に経済合理性はない!」(「地方を殺すな!」 洋泉社MOOK内コラム))
これが、正常な国土の形成と言えるでしょうか?
また、休日のたびに車に何時間も揺られ、巨大モールに着き、人ごみにもまれながら買い物をして、また何時間もかけて岐路に着くという生活を繰り返した家庭、そして子供達は、どうなるのでしょうか?
『(前略)本来、風土というものは、その土地の自然に制約されているものです。自然がその土地の作物や産業を規定し、その結果、その土地の生活や文化を規定する。こうしてできた生活や文化は、それ自体が文化風土や精神風土を形成し、その土地に生まれた人間を、ほかの土地に生まれ育った人間とは異なる人間として育てていく。
(中略)現代では道路が風土を生み出しているとすれば、風土も均質になっているといえる。それは、本来その土地がもっていた個性が失われ、文化が消滅するということなのです。僕はこの「地域固有の文化の喪失」、いいかえれば地域ごとに存在していた“誇りの消滅”というのが、ファスト風土化(※著者はどの都市の郊外も同じような全国チェーン店舗が立ち並ぶ光景を、皮肉を込めて“ファスト風土”と名付けています)の大きな問題だと考えます。
(中略)現代における土地への誇りの喪失は、そこに住む人々の意欲の喪失につながるでしょう。だから、ファスト風土化は下流社会化にもつながるんじゃないかと思いますね。(後略)』
(三浦 展氏著「ファスト風土が日本を壊す!」(「地方を殺すな!」 洋泉社MOOK内コラム))
何度も言いますが、高速無料化は、こうしたファスト風土化に拍車をかけるでしょう。
では、それに対抗するには、どうしたら良いでしょうか?
なまくらは、宮崎なら宮崎で、独自の文化を再構築していくべきだと思います。
ただ、これは非常に難しい方法ですよね。わたしも、良案が思い浮かびません。
しかし、ヒントはあります。
綾町は、昔、夜逃げの町と呼ばれるほど衰退していましたが、今では照葉樹林を資源とした観光だけでなく、有機栽培や低農薬などの野菜・果物づくり、陶芸など、町独自の文化を育て上げ、過疎指定地から脱却しました。町中心部にある「ほんものセンター」は、いつも人で賑わい、周辺の飲食店はタウン宮崎発行のグルメ本「らんらんランチ」で特集を組まれるほどになっています。
先日、なまくらも家族と行きましたが、確かに美味しかったです。
元々、特にこれ、といった資源があるわけでもなかった町が、“変人”町長、故郷田 実氏の働きかけにより、照葉樹林の伐採を中止させ、「比較異(オンリーワン)」を合言葉に、町一丸となってまちづくりを行った結果です。
つまり、先見の明を持った優秀な人が、綾町にいたわけです。勿論、町長のリーダーシップだけでは町全体が変わることはなかったでしょう。やはり、「町を何とかしないといけない」と思った多くの町民がいたからこそ、町長がここまでやり遂げられたのでしょう。
先ほど、「綾町は特にこれ、といった資源があるわけでもなかった」、と書きましたが、実は資源があったのです。その名は「人」。人々の優秀な頭脳とやる気が、まちづくりの起爆剤となり、綾町の成功物語に繋がったのです。
宮崎県の人口は117万人、これだけ多くの頭脳と、東国原知事を誕生させた情熱があります。(知事そのものには個人的に「?」ですが)
きっと、変わることはできます。
しかし、その前に、始末しなければいけない問題も、あるとかないとか・・・↓
(以下、2ちゃんねるより引用)
10 :エージェント・774:2005/08/08(月) 23:31:21 ID:3cSYdPPR ?
661 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします New! 2005/08/08(月) 16:03:28 ID:773SZWAx0
これは去年の参院選の頃に一時期話題になったけど、いつの間にか見かけなくなったコピペ。
はっきり言って、状況証拠からは岡田は黒。
これを広めれば、間違いなく民主党を殺せる。コピペ推奨。
○大店法
「大店立地法」とは1998年5月に成立した(施行は2000年6月)「まちづくり3法」と呼ばれる新法の一つ。
これは通産省がガイドラインを示し、各地方自治体がその管轄をする仕組みになってる。
「大店法」を廃止し新たに施行された「大店立地法」の骨子は、
「店舗周辺の中小小売業者の事業活動の機会の適正な確保」だった出店規制が、
「店舗周辺の生活環境の保持」という大幅な緩和にある。
つまり、店舗予定地から算出される商圏内に中小小売業者がある場合、
一定規模以上の店舗を建設する事が出来なかった訳だ。
だが、この改正によって店舗の商圏内の小売店に配慮しなくてもよくなった為、
郊外の人口密度の低い場所にも、大型の店舗を開店できるようになった。
○元通産官僚 岡田克也
岡田克也(民主党代表)は、当時通産官僚として大店法改正案の内容を知る立場にあり、
同時にイオングループの不動産売買を担当する小会社の取締役を違法に兼務していた。
イオンと通産省が、岡田克也を媒介として「大店立地法」という情報で繋がってても不思議じゃない構図がある。
イオン(旧ジャスコ)は、改正前から郊外地をターゲットに、誰もが出遅れた大規模な店舗展開をできる準備をし、
その結果、それまで業界での双頭の一つダイエーを押し遣るほどの力を得た。
つまり、業界筋じゃ有名な「ジャスコ岡田卓也会長の経営手腕」にも、疑問符が付く疑惑が見え隠れしているわけだ。
岡田克也氏曰くの「父親の持つ不動産関係の会社、岡田興産」の実態・現状がはっきりすれば、
ひょっとしたら単なる「国家公務員法違反」で終わらない可能性がある大問題なんだが、はたして…。
○イオングループと岡田克也に対するチャネラの声
1.ジャスコができると同時に、道路が整備・開通したりする。まさか本人とは・・・
2.涼しい顔して商店街が潰れたのは小泉のせいとか言ってるんだから悪にも程があるよ。
また、今日はいつもより長いです。
民主党は衆院選のマニフェスト(政権公約)で明記した「高速道路の無料化」を、北海道と九州で来年度から先行実施する方針を固めた。複数の関係筋が14日、明らかにした。利用状況や経済効果をにらみながら無料化路線を段階的に拡大していく考えだ。
ただ、これまでの道路建設に伴う約30兆円の有利子負債や道路の維持管理コストをどう捻出(ねんしゅつ)するかはいまだに示されていない。民主党の鳩山由紀夫代表が掲げる「温室効果ガス25%削減」方針にも矛盾するとの指摘もある。
無料化を先行実施するのは、供用されている高速道路約7678キロのうち、北海道エリアの581キロ、九州エリアの794キロ。東名高速など大都市圏をつなぐ主要路線と比べると、交通量が少ない路線だ。
高速道路を無料化すれば、交通渋滞、排ガスによる環境悪化、料金所廃止による雇用問題、他の交通機関への影響-など数々の問題が起きるといわれる。
このため、民主党では、交通量が少なく、限定された地域で先行実施すれば、無料化に伴う悪影響を最小限にとどめることができる上、対策を講じやすいと判断した。加えて地域経済に与える効果などを把握でき、このデータを基に複合的な地域活性化策を策定できるメリットもある。
民主党は、マニフェスト工程表で、平成24年度には首都高速、阪神高速を除くすべての高速道路を「原則無料開放」する方針を示した。これに伴い、民主党は23年度の通常国会で、高速道路を保有する独立行政法人「日本高速道路保有・債務返済機構」を国有化するため法改正する方針。無料化後の高速道路は一般国道の「自動車専用道路」とする方向で検討している。
民主党は経済効果を3年間で2兆円、国内総生産(GDP)を0・41%押し上げると試算している。国交省も20年、首都高速と阪神高速を除く無料化による経済効果を2兆7千億円とする試算をまとめた。
一方、国有化すれば、返済機構が抱える約30兆円の有利子負債は国の債務として計上され、道路の維持管理費や新規建設費は税金で負担することになる。
(以上、MSN産経ニュースより引用)
武坊
だから、わたし達の宮崎自動車道、このあたりが全国に先駆けてタダになる可能性があるということですね?で、九州道もでしょ?だから、福岡まで来年度、いよいよタダになるっていうのが見えてきた、ということですよね。
駆け込みでETC付けた皆さん、それ、あんまり意味無くなりますね(笑)
で、高速が0円になった場合、国交省が自動車の年間利用者が57.5%増えるだろう、と見越しております。で、鉄道に乗る人は10.6%減るだろう、飛行機も4.2%減るだろうというような集計結果を明らかにしております。
ま、色んなところに影響があるんですけれども、取りあえず九州が先駆けてタダになる、て言う事は、今まで商圏を宮崎なら宮崎エリア、せいぜい鹿児島エリアまで入れてたかも知れないけれども、平日も土日も含めてタダ、て言う事になると、ちょっと商圏を広げて考えないといけなくなりますよね?
アウトレットモールが鳥栖にあったでしょ?ああいった所もガソリン代だけで行けてしまうわけだから、宮崎の郊外型のショッピングセンター・モールの敵に、いきなりなるわけですよ。200km離れていようが。
片やこっちは定価で売っている、片や3割、4割引きで売っているとなると、そこでもバチバチ火花が散り始める…
淳ちゃん
勉強不足で申し訳ないけれども、建設予定の高速道路があるわけやろ?それ、ちゃんと期間内にできるんやろか?
武坊
それはまだ、はっきり言ってないですよね。
淳ちゃん
きちんと造ってもらわないと困るし、出来ないと、お客さんは逃げて行ってしまう。やっぱりこれは、どうなるんだろう?ちょっと心配かな?
武坊
よく、高速道路はストロー化現象の象徴だ、と言われていて、便利な道を造ると、力のある方が力のない方のお金、人を吸い上げていく、と言われてました。でも今までは福岡まで行くのに普通車で5,6千円という“通行手形”が要ったわけや。それが関所になってたけど、今度はそのストローが本っ当に通りの良いストローになるわけやから、チューと吸おうと思えば吸えるわけで、本当に勝ち負け明暗分かれると思いますよ?ね?
淳ちゃん
ま、その分例えば通勤とかで高速道路を使えるようになることによって、もっと住みやすい場所があるとか、そういうのがあるのかも分からないけど、まあそれ、1,2年ていうわけじゃないやろうからね。
武坊
何でも功罪両面あるんだろうけれども、この高速タダ、ていうのは、“功”の分より“罪”というか痛む分のケア、どうせケアしなきゃいけないやろ?鉄道にしろ、フェリーなんか直ですよね。でもそれを潰すわけにいかないから、それを税金で助けたりするわけでしょ?
ならば、やっぱり0円じゃなくて、整合性取った方が良いようにありますけれどもね。
淳ちゃん
バランス、ということを考えると、この超高齢化社会において、車の運転をしなくなる人、できなくなる人は増えてくるわけでしょ?そういう方々が利用する公共交通機関の料金が、反対に高くなったらどうするんだろう?
で、ちょっと違う話をして良い?
この間、私はタイのバンコクに行きました。福岡からバンコクまで格安航空券を手に入れ、往復3万8千円でした。で、仕事があったので、行き帰りを飛行機で福岡―宮崎間を利用し、往復2万5千円かかりました。分かります?国内路線が日本は高い、と。これは仕方がないだろう、色んな理由があって。にしても、ユーロ圏であっても、国内あるいは陸続きの隣国に行く料金は、やっぱり安いわ。これでお客を乗せて飛行機を飛ばせて、価格も…
どうなんだろうね?この価格差は。
武坊
淳子さんの場合は2万5千円かけて飛行機乗ったけれども、スケジュールさえ合えば、ガソリン代だけで行けたわけでしょ?て事はさ、そこに物凄い差が生まれるから、じゃあ夜中に着く便でも、兎に角無茶してでも車で行こうとする人は増えますわな。
淳ちゃん
でも、人間歳とると無茶できなくなるでしょ?やっぱそこら辺のバランス、ていうのを考えてほしいな、とふと思った48歳でした(笑)
武坊
どうなんだろう?前にもこの番組で言ったけれども、上限5千円くらいで打ち切り、で良いんじゃない?財源確保できて、それで道路造ります、て言えば良いわぁ。0、て言ったらさぁ、ねぇ?
淳ちゃん
で、それで陸・海・空のバランスを少し考えてもらって、色んなところで補助しないといけないんだろうから、もうちょっと使い勝手の良いような交通手段を作って欲しいな、と改めて思いました。
(書き起こし終わり)
ま、一応正論ですね。
高速道路が無料化すれば、ストロー現象がますます激しくなって、地方都市、特に中心市街地がますます衰退する、という武坊さんの予感、多分当たると思います。
そして、最終的には全国10~30のインターチェンジ近郊に10万㎡クラスの超大型モールと、各地方都市ごとにモールの関連小売業者、もっと具体的に言うと、インターにはイオンモール、各都市にはマックスバリュやホームワイドといった店が立ち並ぶことになるでしょう。
今でさえ、地方中核都市の近郊と、それ以外の市町村の関係は、そうなってますよね。これが、全国規模に拡大される、と考えられるわけです。
国民のほとんどが休日を各地のイオンモールで過ごす世の中・・・ちょっと考えただけで、気持ち悪くないですか?
まあ、そこまで極端にならなくても、地方の中心市街地は確実に衰退します。
そして、そこに至る過程で、小売業界は中心市街地、郊外を問わず、熾烈な過当競争に巻き込まれます。
『(前略)最終的には、持久戦に敗れた多くの事業者が撤退し、(中略)上下水道や道路が整った郊外開発地に大量の空き店舗や駐車場の残骸が発生していることになります。その後始末は行政の手をわずらわせ、結局は増税などを通じて住民や地域の企業に転嫁されます。(後略)』
(藻谷 浩介氏著「『焼畑農業』と化した郊外乱開発に経済合理性はない!」(「地方を殺すな!」 洋泉社MOOK内コラム))
これが、正常な国土の形成と言えるでしょうか?
また、休日のたびに車に何時間も揺られ、巨大モールに着き、人ごみにもまれながら買い物をして、また何時間もかけて岐路に着くという生活を繰り返した家庭、そして子供達は、どうなるのでしょうか?
『(前略)本来、風土というものは、その土地の自然に制約されているものです。自然がその土地の作物や産業を規定し、その結果、その土地の生活や文化を規定する。こうしてできた生活や文化は、それ自体が文化風土や精神風土を形成し、その土地に生まれた人間を、ほかの土地に生まれ育った人間とは異なる人間として育てていく。
(中略)現代では道路が風土を生み出しているとすれば、風土も均質になっているといえる。それは、本来その土地がもっていた個性が失われ、文化が消滅するということなのです。僕はこの「地域固有の文化の喪失」、いいかえれば地域ごとに存在していた“誇りの消滅”というのが、ファスト風土化(※著者はどの都市の郊外も同じような全国チェーン店舗が立ち並ぶ光景を、皮肉を込めて“ファスト風土”と名付けています)の大きな問題だと考えます。
(中略)現代における土地への誇りの喪失は、そこに住む人々の意欲の喪失につながるでしょう。だから、ファスト風土化は下流社会化にもつながるんじゃないかと思いますね。(後略)』
(三浦 展氏著「ファスト風土が日本を壊す!」(「地方を殺すな!」 洋泉社MOOK内コラム))
何度も言いますが、高速無料化は、こうしたファスト風土化に拍車をかけるでしょう。
では、それに対抗するには、どうしたら良いでしょうか?
なまくらは、宮崎なら宮崎で、独自の文化を再構築していくべきだと思います。
ただ、これは非常に難しい方法ですよね。わたしも、良案が思い浮かびません。
しかし、ヒントはあります。
綾町は、昔、夜逃げの町と呼ばれるほど衰退していましたが、今では照葉樹林を資源とした観光だけでなく、有機栽培や低農薬などの野菜・果物づくり、陶芸など、町独自の文化を育て上げ、過疎指定地から脱却しました。町中心部にある「ほんものセンター」は、いつも人で賑わい、周辺の飲食店はタウン宮崎発行のグルメ本「らんらんランチ」で特集を組まれるほどになっています。
先日、なまくらも家族と行きましたが、確かに美味しかったです。
元々、特にこれ、といった資源があるわけでもなかった町が、“変人”町長、故郷田 実氏の働きかけにより、照葉樹林の伐採を中止させ、「比較異(オンリーワン)」を合言葉に、町一丸となってまちづくりを行った結果です。
つまり、先見の明を持った優秀な人が、綾町にいたわけです。勿論、町長のリーダーシップだけでは町全体が変わることはなかったでしょう。やはり、「町を何とかしないといけない」と思った多くの町民がいたからこそ、町長がここまでやり遂げられたのでしょう。
先ほど、「綾町は特にこれ、といった資源があるわけでもなかった」、と書きましたが、実は資源があったのです。その名は「人」。人々の優秀な頭脳とやる気が、まちづくりの起爆剤となり、綾町の成功物語に繋がったのです。
宮崎県の人口は117万人、これだけ多くの頭脳と、東国原知事を誕生させた情熱があります。(知事そのものには個人的に「?」ですが)
きっと、変わることはできます。
しかし、その前に、始末しなければいけない問題も、あるとかないとか・・・↓
(以下、2ちゃんねるより引用)
10 :エージェント・774:2005/08/08(月) 23:31:21 ID:3cSYdPPR ?
661 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします New! 2005/08/08(月) 16:03:28 ID:773SZWAx0
これは去年の参院選の頃に一時期話題になったけど、いつの間にか見かけなくなったコピペ。
はっきり言って、状況証拠からは岡田は黒。
これを広めれば、間違いなく民主党を殺せる。コピペ推奨。
○大店法
「大店立地法」とは1998年5月に成立した(施行は2000年6月)「まちづくり3法」と呼ばれる新法の一つ。
これは通産省がガイドラインを示し、各地方自治体がその管轄をする仕組みになってる。
「大店法」を廃止し新たに施行された「大店立地法」の骨子は、
「店舗周辺の中小小売業者の事業活動の機会の適正な確保」だった出店規制が、
「店舗周辺の生活環境の保持」という大幅な緩和にある。
つまり、店舗予定地から算出される商圏内に中小小売業者がある場合、
一定規模以上の店舗を建設する事が出来なかった訳だ。
だが、この改正によって店舗の商圏内の小売店に配慮しなくてもよくなった為、
郊外の人口密度の低い場所にも、大型の店舗を開店できるようになった。
○元通産官僚 岡田克也
岡田克也(民主党代表)は、当時通産官僚として大店法改正案の内容を知る立場にあり、
同時にイオングループの不動産売買を担当する小会社の取締役を違法に兼務していた。
イオンと通産省が、岡田克也を媒介として「大店立地法」という情報で繋がってても不思議じゃない構図がある。
イオン(旧ジャスコ)は、改正前から郊外地をターゲットに、誰もが出遅れた大規模な店舗展開をできる準備をし、
その結果、それまで業界での双頭の一つダイエーを押し遣るほどの力を得た。
つまり、業界筋じゃ有名な「ジャスコ岡田卓也会長の経営手腕」にも、疑問符が付く疑惑が見え隠れしているわけだ。
岡田克也氏曰くの「父親の持つ不動産関係の会社、岡田興産」の実態・現状がはっきりすれば、
ひょっとしたら単なる「国家公務員法違反」で終わらない可能性がある大問題なんだが、はたして…。
○イオングループと岡田克也に対するチャネラの声
1.ジャスコができると同時に、道路が整備・開通したりする。まさか本人とは・・・
2.涼しい顔して商店街が潰れたのは小泉のせいとか言ってるんだから悪にも程があるよ。
2009年08月25日
高速無料を考える
以前の記事で「高速1000円を考える」と題して持論めいたものを書きましたが、その後、高速無料化について次のような意見を見つけ、なるほど、と思ったので転載します。
(前略)
民主党が掲げる「高速道路の無料化」は、低炭素社会づくりに逆行する施策であろう。国民生活や企業活動のコストが引き下げられ、地域活性化も期待されるとしているが、車の交通量増大による二酸化炭素の増加は明らかだ。
高速無料化には、さらに重大な弊害が潜む。「郊外の拡大」だ。安い土地が利用可能となることで都市のさまざまな商業拠点が高速道路を利用して遠くへ移る。
低炭素社会での具体的な都市の姿であるコンパクトシティーとは相いれない方向だ。都市がいったん拡大すると元に戻すのは容易でない。肥大した都市は、エネルギーとコストを浪費する。
今年12月には、ポスト京都の取り組みを決める国連気候変動枠組み条約締約国会議が開かれる。日本にも他国同様、国益を視野に収めた交渉戦略が必要だ。それが可能な政党かどうか。衆院選での判断材料のひとつにしたい。
(MSN産経ニュース 【主張】地球環境公約 25%削減は国が転倒する http://sankei.jp.msn.com/politics/election/090819/elc0908190305006-n1.htm より)
現与党案の高速1000円と民主党案の高速無料化、どちらも経済ならびに環境に与えるインパクトは大きいと思っていましたが、大きな違いは
2年間のみの時限的な政策か、半永久的な政策か
だったのですね。
つまり、2年間限定となると、わざわざ店を新規出店したり、店舗を拡大したり、という投資行動にまでは結びつかないが、半永久的な政策になると、投資行動にまで結びついちゃう、という事ですね。
インターのある町は活性化する?それは幻想に過ぎないでしょう。だって、全国のインター近辺で一斉に大規模開発が起これば、(後述するまちづくり3法による規制はあるが、それでも防ぎきれないでしょう)オーバーストアーとなり、共倒れになるのは目に見えています。しかも、真っ先に倒れるのは、昔からある地元の小売店…
よって、高速無料化は、小泉改革によって虐げられた地方がさらに衰退する危険があるのです。
それから、近年成立したまちづくり3法により、大規模小売店舗の郊外立地が厳しく制限されるようになりました。
仮に高速無料化となり、地方のインター付近に開発の波が押し寄せた時、最も競争に有利なのが、法改正前に駆け込みで出店ラッシュを行ったイオングループだと思います。新規出店は手続きに時間がかかりますからね。
さて、ここでクイズです。
そのイオングループの中核企業、イオン株式会社の社長である岡田元也氏の実弟は現在国会議員ですが、何党の幹事長でしょうか?
いやあ、目線を変えると、色々見えてくるものがありますねぇ~
岡
(前略)
民主党が掲げる「高速道路の無料化」は、低炭素社会づくりに逆行する施策であろう。国民生活や企業活動のコストが引き下げられ、地域活性化も期待されるとしているが、車の交通量増大による二酸化炭素の増加は明らかだ。
高速無料化には、さらに重大な弊害が潜む。「郊外の拡大」だ。安い土地が利用可能となることで都市のさまざまな商業拠点が高速道路を利用して遠くへ移る。
低炭素社会での具体的な都市の姿であるコンパクトシティーとは相いれない方向だ。都市がいったん拡大すると元に戻すのは容易でない。肥大した都市は、エネルギーとコストを浪費する。
今年12月には、ポスト京都の取り組みを決める国連気候変動枠組み条約締約国会議が開かれる。日本にも他国同様、国益を視野に収めた交渉戦略が必要だ。それが可能な政党かどうか。衆院選での判断材料のひとつにしたい。
(MSN産経ニュース 【主張】地球環境公約 25%削減は国が転倒する http://sankei.jp.msn.com/politics/election/090819/elc0908190305006-n1.htm より)
現与党案の高速1000円と民主党案の高速無料化、どちらも経済ならびに環境に与えるインパクトは大きいと思っていましたが、大きな違いは
2年間のみの時限的な政策か、半永久的な政策か
だったのですね。
つまり、2年間限定となると、わざわざ店を新規出店したり、店舗を拡大したり、という投資行動にまでは結びつかないが、半永久的な政策になると、投資行動にまで結びついちゃう、という事ですね。
インターのある町は活性化する?それは幻想に過ぎないでしょう。だって、全国のインター近辺で一斉に大規模開発が起これば、(後述するまちづくり3法による規制はあるが、それでも防ぎきれないでしょう)オーバーストアーとなり、共倒れになるのは目に見えています。しかも、真っ先に倒れるのは、昔からある地元の小売店…
よって、高速無料化は、小泉改革によって虐げられた地方がさらに衰退する危険があるのです。
それから、近年成立したまちづくり3法により、大規模小売店舗の郊外立地が厳しく制限されるようになりました。
仮に高速無料化となり、地方のインター付近に開発の波が押し寄せた時、最も競争に有利なのが、法改正前に駆け込みで出店ラッシュを行ったイオングループだと思います。新規出店は手続きに時間がかかりますからね。
さて、ここでクイズです。
そのイオングループの中核企業、イオン株式会社の社長である岡田元也氏の実弟は現在国会議員ですが、何党の幹事長でしょうか?
いやあ、目線を変えると、色々見えてくるものがありますねぇ~
岡
2009年08月19日
高速1000円を考える
昨日のニュースは、高速1000円の影響、ということがテーマだったようです。
上信越道で追突事故、2人死亡5人重傷
17日午前0時25分頃、群馬県高崎市吉井町黒熊の上信越自動車道上り線で、渋滞の最後尾で停止していた埼玉県春日部市薄谷、無職斎藤武夫さん(70)の乗用車に長野市七瀬中町、会社員石毛正義さん(61)のトラックが追突した。
斎藤さんの車は前の大型トラックとの間に挟まれ、斎藤さんと娘婿の湊一茂さん(38)が頭や胸を打つなどして死亡。湊さんの妻の日登美さん(42)と子供3人、石毛さんの計5人が足を骨折するなどの重傷を負った。
群馬県警の発表によると、現場は見通しの良い直線。事故当時はUターンラッシュが続いており、藤岡ジャンクションから現場まで約8・2キロの渋滞が起きていた。この事故で、現場周辺は約5時間20分にわたって通行止めになった。
(読売新聞)
武坊
今までのETC割引がなかった頃との違いは、考えられないような遠方ナンバーの車が増えましたよね。青森ナンバーとか。
そして、もうひとつの特徴として、軽自動車が増えましたよね。卒業旅行か何かで4人がぎゅうぎゅうになって乗ってたりするの。
昔は100キロくらいで走ったらすぐにオーバーヒートしてたけど、今はエンジンが良いもんだから高回転でも伸びが良い。あれで120キロくらいですっ飛ばしてる軽が結構多くてね、あれは危ないよね。
で、台数が多いから、走行車線と追い越し車線の役割が無くなって、遅い車もずっと追い越し車線を走ってるの。
そうすると、やっぱり皆イライラするじゃない。
で、お盆が始まる前にこういう事故がありました。追い越し車線を走っていたノロノロ運転の車を追い越そうとして、内側の走行車線から加速付けて行ってたら、スピンしてしまって、後部座席に乗っていた女の子が車外に投げ出されて、反対側の車線に飛び出してしまって重傷を負った事故がありました。
まあ、高速1000円になって皆助かった、て利用していますけど、それによって色んな事が見えてきた部分がありますよね。
淳ちゃん
ホリデードライバー、ていうんですか?休みの時しか運転しないドライバーもいると思うけど、やっぱり最近運転してて思いません?イラつき運転が多いですよね。
となれば、普段あまり運転しない方は特に、高速道路とか注意した方が良いと思う。
武坊
そうねえ。
今まさに選挙戦に入ろうとしてて、高速料金もマニフェストに乗っかってたりするわけでしょ?
何党が与党になるかはともかくとして、この高速料金てのは確かに安くすれば皆便利になるんだけれども、妥当な線ではないね、1000円てのはやっぱり。
0円も多分妥当な線じゃないと思います。どっかから財源持ってこにゃいかんわけだから。
わたし思うんだけれど、5000円くらいでどうでしょうか?5000円で上限打ち切り、というふうにすれば、例えば宮崎から福岡が5000円くらいですか?福岡より遠くに行けば走り放題、となれば、九州内はほぼ実費で走らないといけないわけでしょ?
人間ひとりが運転できる距離、て知れてるわけじゃないですか。
ならば、3000円とか5000円とかある程度打ち出さないと、既存の公共交通機関が圧迫されてしまって、たまらんですよ。
淳ちゃん
極端すぎるから、皆欲がでちゃうんよね。だって、1000円だもん、どこまで行ったって。
武坊
ちゃんと住み分けが必要だと思うの。なぜか、て、お盆とか正月とかは公共交通機関は正規料金でやってるわけでしょ?そこへ持ってきて何で道路だけ格安になるわけ?
だから、一人分の旅費以下で、5人が旅行に行けちゃう。じゃあ、その差額はどうしてんの、というと全部税金で補填しているんですけれども、なんかそれも違うような気がしてね。財源がそれこそ、あやふやじゃないですか。
ならばやっぱり利用者負担が原則でしょうから、もうちょっと高値で良いんじゃないかな。
淳ちゃん
帰りが私、福岡空港だったんですよ。福岡空港で降りて、都市高速が600円、6,7キロくらいでしょう。その後、宮崎まで1000円ですよ。
私は欲深いので、600円と1000円について、貪欲に物事を考えてしまうんですよね。(笑)
そのバランスの悪さをずっと車の中で考えながら…
武坊
そうやろ!?高速料金1000円で、北熊本SAで小龍包を家族で食べたら、あっという間に1500円かかってしまったわ!そっちの方が高いの。(笑)
だからモノの値段てさ、適正価格、てあるよね。そのあたり、どの党がなってもきちっとやってほしいとおもいますけどね。
(以上、書き起こし終わり)
まず、これだけは皆さんに守ってもらいたいのが、高速道路で渋滞に巻き込まれ、最後尾になったら、必ずハザードを点けて下さい。
高速道路て信号がないせいか、前の車はずっと走っているもの、と考えがちになります。だから、渋滞などで前の車が停止してても、気づくのが遅れるんですね。
その際、点きっぱなしのブレーキランプよりはるかに視認性に優れるのが、点滅しているハザードなのです。
だから、渋滞の最後尾ではハザードで後続車に異常を知らせることが、自分の命を守ることになります。
それから、前車とは十分な車間距離をあけて停止してください。(あまりあけすぎると、隣から割り込まれて意味がありませんが)
そして、停止中は常にバックミラーで後ろの様子を確認するようにしておけば、万が一追突されそうになっても、少し前に進むなど、対処が可能になります。
渋滞に巻き込まれたら、常に周りに気を配り、最悪の事態を想定することが大切、ということです。
さて、高速1000円、なまくらは1回しかその恩恵に与っておりませんが、他の交通機関とのバランスは確かに悪いですな。
というか、コストを削減して、云々というレベルを超えているため、フェリー会社なんかは特に悲鳴をあげているのは周知のとおりです。
元々、去年の原油高を受けた対策として、高速値下げ案が浮上した、と記憶しております。つまり、物流業界対策ですね。
ところがリーマンショック以降、物流対策がいつの間にか景気対策、消費のカンフル剤になってしまった。
当初案では恩恵を受けるはずだったトラックは値下げされないどころか、大量発生したマイカーに邪魔され、かえって不利益を被っている、そんな構図になっています。
一方で、四国などは観光に沸いていますよね。
そりゃそうでしょう。今まで本四3架橋どれを使っても、往復で1万円以上取られていたのが、往復2000円で済むんですから。
近畿圏の人達が、「今まで橋が高くて行ったことなかったけど、1000円で行けるし、片道1時間もあれば着くから、この際遊びに行ってみるか。」
となるのはごく自然な反応だと思います。
四国の観光地は休みのたびに大賑わい、四国経済の活性化に繋がっています。
(で、東九州道のように暫定1車線が多い四国の高速道路は、休みのたびに渋滞を起こしているようです。)
結局、1つの政策には必ず功罪ある、てことで、得する人もいれば、損する人もいるわけですね。制度開始から半年近く経つわけですから、どちらのウエイトが大きかったかをそろそろ検証しないと、継続するにしても、廃止するにしても、あるいは無料にするにしても、後の政策の立てようがないと思うのですが…
ま、なまくら私案では、トラックを地方の高速限定で上限5000円くらいにして物流コストを下げつつ、公共交通機関の税金(着陸料や港湾使用料など)を期間限定で免除して、運賃割引への還元を促し、景気対策、環境対策とする、なんて考えたりします。
え、財源!?色々あるでしょ?パチンコ課税とか、マスコミの低すぎる電波使用料を引き上げるとか、国旗を斬り裂いてニコイチの党旗を作ったところには罰金1億円とか。(笑)
上信越道で追突事故、2人死亡5人重傷
17日午前0時25分頃、群馬県高崎市吉井町黒熊の上信越自動車道上り線で、渋滞の最後尾で停止していた埼玉県春日部市薄谷、無職斎藤武夫さん(70)の乗用車に長野市七瀬中町、会社員石毛正義さん(61)のトラックが追突した。
斎藤さんの車は前の大型トラックとの間に挟まれ、斎藤さんと娘婿の湊一茂さん(38)が頭や胸を打つなどして死亡。湊さんの妻の日登美さん(42)と子供3人、石毛さんの計5人が足を骨折するなどの重傷を負った。
群馬県警の発表によると、現場は見通しの良い直線。事故当時はUターンラッシュが続いており、藤岡ジャンクションから現場まで約8・2キロの渋滞が起きていた。この事故で、現場周辺は約5時間20分にわたって通行止めになった。
(読売新聞)
武坊
今までのETC割引がなかった頃との違いは、考えられないような遠方ナンバーの車が増えましたよね。青森ナンバーとか。
そして、もうひとつの特徴として、軽自動車が増えましたよね。卒業旅行か何かで4人がぎゅうぎゅうになって乗ってたりするの。
昔は100キロくらいで走ったらすぐにオーバーヒートしてたけど、今はエンジンが良いもんだから高回転でも伸びが良い。あれで120キロくらいですっ飛ばしてる軽が結構多くてね、あれは危ないよね。
で、台数が多いから、走行車線と追い越し車線の役割が無くなって、遅い車もずっと追い越し車線を走ってるの。
そうすると、やっぱり皆イライラするじゃない。
で、お盆が始まる前にこういう事故がありました。追い越し車線を走っていたノロノロ運転の車を追い越そうとして、内側の走行車線から加速付けて行ってたら、スピンしてしまって、後部座席に乗っていた女の子が車外に投げ出されて、反対側の車線に飛び出してしまって重傷を負った事故がありました。
まあ、高速1000円になって皆助かった、て利用していますけど、それによって色んな事が見えてきた部分がありますよね。
淳ちゃん
ホリデードライバー、ていうんですか?休みの時しか運転しないドライバーもいると思うけど、やっぱり最近運転してて思いません?イラつき運転が多いですよね。
となれば、普段あまり運転しない方は特に、高速道路とか注意した方が良いと思う。
武坊
そうねえ。
今まさに選挙戦に入ろうとしてて、高速料金もマニフェストに乗っかってたりするわけでしょ?
何党が与党になるかはともかくとして、この高速料金てのは確かに安くすれば皆便利になるんだけれども、妥当な線ではないね、1000円てのはやっぱり。
0円も多分妥当な線じゃないと思います。どっかから財源持ってこにゃいかんわけだから。
わたし思うんだけれど、5000円くらいでどうでしょうか?5000円で上限打ち切り、というふうにすれば、例えば宮崎から福岡が5000円くらいですか?福岡より遠くに行けば走り放題、となれば、九州内はほぼ実費で走らないといけないわけでしょ?
人間ひとりが運転できる距離、て知れてるわけじゃないですか。
ならば、3000円とか5000円とかある程度打ち出さないと、既存の公共交通機関が圧迫されてしまって、たまらんですよ。
淳ちゃん
極端すぎるから、皆欲がでちゃうんよね。だって、1000円だもん、どこまで行ったって。
武坊
ちゃんと住み分けが必要だと思うの。なぜか、て、お盆とか正月とかは公共交通機関は正規料金でやってるわけでしょ?そこへ持ってきて何で道路だけ格安になるわけ?
だから、一人分の旅費以下で、5人が旅行に行けちゃう。じゃあ、その差額はどうしてんの、というと全部税金で補填しているんですけれども、なんかそれも違うような気がしてね。財源がそれこそ、あやふやじゃないですか。
ならばやっぱり利用者負担が原則でしょうから、もうちょっと高値で良いんじゃないかな。
淳ちゃん
帰りが私、福岡空港だったんですよ。福岡空港で降りて、都市高速が600円、6,7キロくらいでしょう。その後、宮崎まで1000円ですよ。
私は欲深いので、600円と1000円について、貪欲に物事を考えてしまうんですよね。(笑)
そのバランスの悪さをずっと車の中で考えながら…
武坊
そうやろ!?高速料金1000円で、北熊本SAで小龍包を家族で食べたら、あっという間に1500円かかってしまったわ!そっちの方が高いの。(笑)
だからモノの値段てさ、適正価格、てあるよね。そのあたり、どの党がなってもきちっとやってほしいとおもいますけどね。
(以上、書き起こし終わり)
まず、これだけは皆さんに守ってもらいたいのが、高速道路で渋滞に巻き込まれ、最後尾になったら、必ずハザードを点けて下さい。
高速道路て信号がないせいか、前の車はずっと走っているもの、と考えがちになります。だから、渋滞などで前の車が停止してても、気づくのが遅れるんですね。
その際、点きっぱなしのブレーキランプよりはるかに視認性に優れるのが、点滅しているハザードなのです。
だから、渋滞の最後尾ではハザードで後続車に異常を知らせることが、自分の命を守ることになります。
それから、前車とは十分な車間距離をあけて停止してください。(あまりあけすぎると、隣から割り込まれて意味がありませんが)
そして、停止中は常にバックミラーで後ろの様子を確認するようにしておけば、万が一追突されそうになっても、少し前に進むなど、対処が可能になります。
渋滞に巻き込まれたら、常に周りに気を配り、最悪の事態を想定することが大切、ということです。
さて、高速1000円、なまくらは1回しかその恩恵に与っておりませんが、他の交通機関とのバランスは確かに悪いですな。
というか、コストを削減して、云々というレベルを超えているため、フェリー会社なんかは特に悲鳴をあげているのは周知のとおりです。
元々、去年の原油高を受けた対策として、高速値下げ案が浮上した、と記憶しております。つまり、物流業界対策ですね。
ところがリーマンショック以降、物流対策がいつの間にか景気対策、消費のカンフル剤になってしまった。
当初案では恩恵を受けるはずだったトラックは値下げされないどころか、大量発生したマイカーに邪魔され、かえって不利益を被っている、そんな構図になっています。
一方で、四国などは観光に沸いていますよね。
そりゃそうでしょう。今まで本四3架橋どれを使っても、往復で1万円以上取られていたのが、往復2000円で済むんですから。
近畿圏の人達が、「今まで橋が高くて行ったことなかったけど、1000円で行けるし、片道1時間もあれば着くから、この際遊びに行ってみるか。」
となるのはごく自然な反応だと思います。
四国の観光地は休みのたびに大賑わい、四国経済の活性化に繋がっています。
(で、東九州道のように暫定1車線が多い四国の高速道路は、休みのたびに渋滞を起こしているようです。)
結局、1つの政策には必ず功罪ある、てことで、得する人もいれば、損する人もいるわけですね。制度開始から半年近く経つわけですから、どちらのウエイトが大きかったかをそろそろ検証しないと、継続するにしても、廃止するにしても、あるいは無料にするにしても、後の政策の立てようがないと思うのですが…
ま、なまくら私案では、トラックを地方の高速限定で上限5000円くらいにして物流コストを下げつつ、公共交通機関の税金(着陸料や港湾使用料など)を期間限定で免除して、運賃割引への還元を促し、景気対策、環境対策とする、なんて考えたりします。
え、財源!?色々あるでしょ?パチンコ課税とか、マスコミの低すぎる電波使用料を引き上げるとか、国旗を斬り裂いてニコイチの党旗を作ったところには罰金1億円とか。(笑)



